保育士5年目になります。保育士に向いてないので辞めたいですが、なかなか踏ん切りがつきません。
2022/07/28

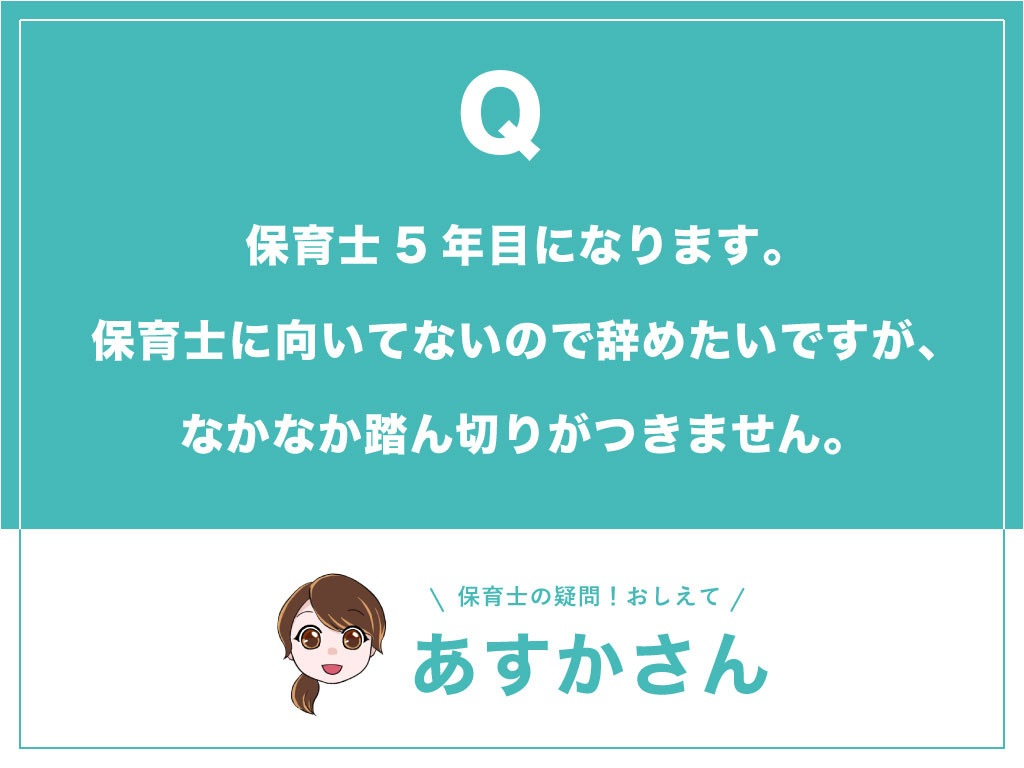
5年目の保育士は保育園では中堅と言われるようになる時期です。
仕事も担任だけではなく、少しずつリーダー的なポジションとなってきて仕事の全体をみながら責任者としての仕事をするようにもなります。
仕事の内容が変わることで保育士に向いていないのではないかと、保育士自体を辞めてしまいたいと考える人も多くなります。
今回は、5年目の保育士が退職を考えるとき、どのような理由があるかや、実際に辞める時に起こるトラブルについてご紹介します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ30年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
保育士の離職は5年未満が一番多い!
厚生労働省「保育士の現状と主な取組」によると、常勤保育士の経験年数別の人数は、経験年数2年未満の保育士で「15.5%」、2~4年未満の保育士で「13.3%」、4~6年未満の保育士で「11.1%」となっています。
合計すると、6年未満の保育士が全体の39.9%を占めており、現職の保育士の約4割が6年未満の保育士であることがわかります。
保育士5年目で向いてない、辞めたいと思う主な理由
保育士に向いていないと思う理由はさまざまですが、ここからもう少し詳細に5年目の保育士が辞めたいと思う理由を具体的にご紹介します。
理由1:仕事量の多さについていけない
ここ数年は保育士不足の影響もあり、保育士一人ひとりに対する仕事量が増えています。
また、5年目になるまで年次が上がるたびに立場も上がり、業務が増えるにも関わらず後輩保育士が定着しないなど、仕事をうまく後輩に引き継ぐことができない状況も生まれています。
年々増えていく仕事量の多さに、この先の将来を考えると保育士という仕事を辞めたいと考えるようになります。
理由2:性格的に向いていない
保育士の多くは子どもが好きで、その成長を支援したいという理由から保育士になっています。
しかし、実際の保育士の仕事は子どもとただ遊んでいるだけの仕事ではありません。
命の責任を請け負い、時に厳しく指導することも必要です。
また、保護者対応や事務作業など、保育以外の仕事も多くあり、イメージしていた保育士の仕事とのギャップに「性格上向いていないのでは?」と感じることが多くなり、保育士を辞めたいと感じてしまうようです。
理由3:責任のある仕事が多くなり、プレッシャーに耐えられない
5年目の保育士となると、保育園では中堅と言われることもあります。
早い方だと、クラス担任という仕事だけでなく、職務分野別リーダーという職務にキャリアアップすることもあります。
キャリアアップ自体は喜ぶことではありますが、まだ仕事に対して自信が持てず、不安を感じてプレッシャーになってしまうことがあります。
こうしたプレッシャーに耐えられなくなった場合、今後のキャリアプランに不安を感じたり、キャリアアップすること自体を怖いと感じたりしてしまう場合に退職を考えるようになります。
理由4:保護者対応が慣れない
保護者対応を苦手とする保育士は少なくありません。
日々の送迎時の短い時間で的確なコミュニケーションが求められる保護者対応は、言い方や伝え方を間違えると大きな問題に発展することもあります。
また、モンスターペアレンツと言われるクレーマーに近い保護者の存在も近年増加してきました。
周囲からは「5年目なので保護者対応も完璧にできて当たり前」というプレッシャーの中、保護者対応をしなくてはならないストレスに耐えかねる保育士も多くいます。
理由5:給料や勤務体型に不満を感じる
保育士の給料は年々上がっていますが、拘束時間や勤務時間を考慮するとまだまだ高いとは言えません。
給料が上がりにくいことや、そもそも給料が低いことが、保育士を辞める理由として非常に多いとされています。
また、シフト制ではあるものの、早朝や夕方遅くまでの勤務体制がローテーションすることにより、生活のリズムが整わないこともあります。
このような理由から、将来的にずっと保育士を続けていけるのか不安になり、退職を考えるようになる場合があります。
理由6:職場の人間関係がうまくいかない
保育士の職場は女性が多く、うまく人間関係が築けているときは良いですが、一度ギスギスし始めるとどうすることもできなくなります。
また、職員室という場は、誰かが入ってくることが少なく、いじめやパワハラなどがあった場合に発覚することがなく、閉鎖的な場所になりやすいことも人間関係を拗らせる要因の一つです。
保育士にとって、園内の人間関係は退職理由の常に上位に来る理由の一つです。
保育士自体ではなく、その保育園や保育士としての働き方に自分が合っていないだけかも?
保育士を辞めたいと考えたとき、保育士自体が向いてないのか、保育園に合っていないのかが曖昧になっている方は非常に多いです。
まずは、自分が退職をしようと思った理由について、しっかりと考えることが必要です。
例えば、人間関係がうまくいかない、給料などの労働条件への不満、仕事量の多さなどは確実に「保育園に合っていない」ということに分類され、保育園を変えることでうまくいくことがあります。
また、責任のある仕事が多くなり、プレッシャーに耐えられないなどは、そもそも担任などにならないような職種や、保育士の働き方(派遣保育士など)を探せば悩みを解消することができます。
特に派遣保育士は、保育補助などのサポート的な立場で働くことになるので、担任業務やリーダー業務が負担になって辞めたいと感じている人にとっては、肩の荷を下ろして働ける雇用形態と言えます。
派遣にあまり良いイメージを持っていない方もいると思いますが、実は保育士の場合は、給与面でも雇用面でも安定した働き方です。
給与面から見ると、確かにボーナスがある正職員のほうが年収は高いものの、月給で比較すると正職員と派遣の間にそれほど差はありません。
また、保育士は慢性的な人手不足なので、よほど問題がない限り派遣切りにあうこともありません。
このように、派遣保育士は世間のイメージとは異なり、自分らしく柔軟に安定して働けるので、「保育士の仕事は好きだけど、仕事の負担が大きいのはツラい」「もっと自分のペースで働きたい」という方にぴったりです。
もちろん、派遣保育士になったからといって、この先もずっと派遣で働かなければということはなく、「正職員に戻りたい」と思ったらいつでも戻ることができます。
派遣として働く際に登録する人材派遣会社は、派遣のみを扱っているイメージがありますが、明日香ではパート・アルバイトから正職員の求人まで幅広く取り扱っています。
専任コーディネーターが現在抱えている悩みや、今後の希望をヒアリングしながら、ライフスタイルに合わせたお仕事を提案することが可能です。
保育士に向いていないと感じたり、仕事量が負担になっていると感じたりした時は、派遣保育士という働き方を視野に入れて、自分に合った働き方や職種を探していきましょう。
5年目の保育士が辞めたいと思った場合、体調やメンタル面の余裕で転職や退職を判断しよう!
5年目になった保育士が退職を考えた場合、まずは辞めたい理由を冷静に判断しましょう。
辞める理由が「保育園を変えること」で改善することであれば、転職活動を始めてみることがおすすめです。
ただし、今の不満が他の保育園で必ずしも解決できるとは限りません。
その現実を見ることで、今の保育園の問題を冷静に考えることにもつながります。
保育士自体が向いてないのではないかと考えた時も、同じように他業種の転職を前提に活動を開始してみましょう。
転職の理由が「体調やメンタル面」にある場合は、まずは自分を大切にすることが必要です。
休職などを申し出て、休養を取ることで冷静に判断できるようにもなります。
休養を取った上で、これ以上続けることができないとなった場合は、退職の判断をするようにしましょう。
5年目の保育士が辞める一般的なフロー
5年目の保育士が退職する一般的な流れは、まず退職の意思を伝えることから始まります。
退職の意思は、法的には退職希望日の14日前までに申告をするようになっていますが、一般的には1ヶ月程度前に申告するのが良いとされています。
まずは直属の上司に退職意思を伝え、その後園長に伝えます。
園長に伝えた後に、保育園側から退職に関する書類等が発行されますので提出します。
退職日には、保険証や貸与品の返却を行い退職となります。
一緒に働く同僚などに伝える場合は、保育園側の指示に従うようにしましょう。
職場の環境などに配慮して情報の解禁日を設ける保育園もあります。
また、引き継ぎについても後任者が困ることのないように、できる限り行うことで、あなた自身の今後の成長に繋がります。
子どもたちや保護者へ退職を伝えるかどうかも保育園の方針によります。
関わりのあった方々へ直接伝えたい思いがあったとしても、今後の影響を考えて退職後にプリントで伝えるなど保育園側にも方針があります。
周囲への混乱を招かないためにも、退職についてどのように伝えるかは、園長や上司に聞いてみてから進めるようにしましょう。
5年目の保育士が辞める上でよくあるトラブルとその対処法
仕事も理解し、重要なポジションを任されるようになった5年目の保育士が「辞めたい」と考え始めると、さまざまなトラブルがあります。
具体的にどのようなトラブルがあるか、事前に知っておくことで対応も変わります。
ここからは、よくあるトラブルについて解説します。
【1】引き留めが強く、園がなかなか休職や退職に応じてくれない
人員不足に悩む保育園では、仕事を安心して任せられる保育士に辞められることは大きな痛手です。
そのため、周囲からは「辞めないでほしい」というプレッシャーがかかり、自分の意思を示すことができない状態に追い込まれることがあります。
引き留めが強く、園がなかなか休職や退職に応じてくれない場合は、労働基準監督署などの第三者機関に相談しましょう。
【2】次の職場でうまくいくかが心配
退職後、次の保育園で保育士をするにしても、別の職種につくにしても、「また同じような問題が出てしまうのでは」と心配になって、退職に踏み切れない方もいます。
慎重に判断することは大切なことですが、モヤモヤしたストレスを抱えたまま働いていると、体調やメンタルに支障が出てくることがあります。
体調やメンタルに支障が出ている場合、次の職場では紹介予定派遣など雇用形態を変更する選択もあります。
紹介予定派遣は、一定の期間を派遣社員として勤務し、実際の職場をみた上で双方の合意により、直接雇用へ変更する雇用形態です。
人材派遣会社など、転職のプロにも相談できるので、心配な場合は転職活動を一人で進めることなく、まずは転職エージェントや人材派遣会社に相談しましょう。
【3】なんとなくキャリアがもったいない気がして踏ん切りがつかない
せっかく5年間という保育士キャリアを築き、ある程度のポジションについている場合は、これまで頑張ってきた保育園を退職することにもったいなさを感じることがあります。
そして、キャリアアップのためには、転職するよりも同じ保育園で勤務し続ける方が近道かもしれません。
これからのキャリアをどのように築きたいのか、長期的な視点で考え、転職をするかどうかについて自分なりにしっかりと考えましょう。
自分自身が今後どうなりたいかを優先して考えていくことが大切です。
【4】周りに悪いと思ってなかなか踏ん切りがつかない
人員不足の保育園が多い中、自分が辞めてしまうことによって同僚保育士に負担がかかることを心配し、辞めることに決心がつかないこともあります。
しかし、「同僚保育士に迷惑がかかってしまうのでは?」という心配は、あなたにとってプラスにはなりません。
時には他人の目を気にすることなく、自分にとって優先すべきことは何かをしっかり考え、自分なりに出した結論を優先するようにしましょう。
【5】園長や上司との折り合いが悪く、なかなか相談自体ができない
退職の第一歩は、園長や上司へ退職意思を伝えることですが、そもそも人間関係が悪く、退職の意思を伝えられない、聞いてもらえない場合もあります。
その場合は、住んでいる地域の労働基準監督署にある退職相談窓口に相談してみるのがおすすめです。
退職に関するトラブルは、労働基準監督署が直接介入するわけではありません。
しかし、窓口の相談員たちは数々の退職に関する相談を受けているため、個々の状況に応じた解決手段について相談に乗ってくれます。
最近では、退職代行サービスもあり、どうしても直接交渉ができない場合は、こうしたサービスを利用することも検討してみましょう。
5年目で辞めたいと思うことはよくある!辞めたいと思ったら、まずは体調で判断して行動しよう!
保育士5年目になると、仕事の幅も増え、退職を考えることはよくあることです。
辞めたいと考えた時、すでに体調やメンタルに支障をきたしている場合は、ゆっくりと休養できる方法を探しましょう。
退職や休職などさまざまな方法があるので、思い詰める前に身体を労わることを考え、その後ゆっくり判断するようにしましょう。
心身ともに限界が来ている場合は、すぐに休養をとることが大切です。
まだ余裕があり、働き続けながら体調を整えたい場合は、派遣保育士として働くのも1つの方法です。
もし、相談したいことがあれば、まずは次の登録フォームから保育士登録をして、専任コーディネーターに今抱える悩みなどを相談してみてください。
カテゴリ
保育士キャリア
ずっと保育士は、保育のお仕事を始めたい、転職・復職したい方にライフステージにあった保育のお仕事をご紹介したい。そして保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援し続けたい、という想いでサービスを運営しています。
60秒で完了!無料会員登録をする
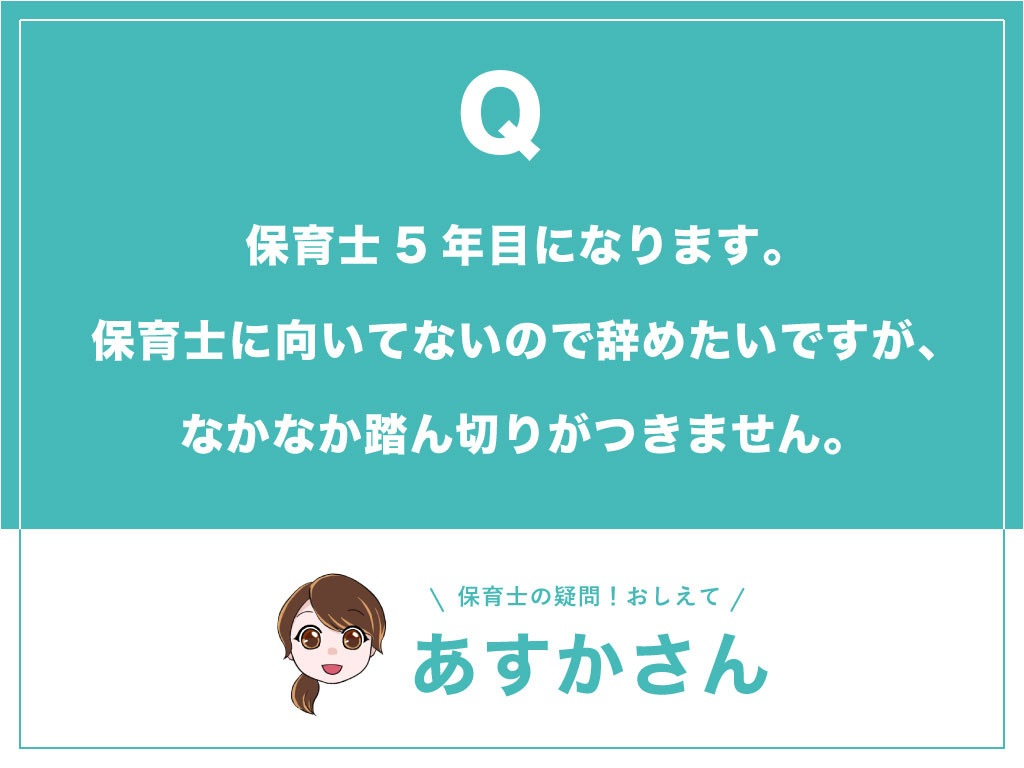
5年目の保育士は保育園では中堅と言われるようになる時期です。
仕事も担任だけではなく、少しずつリーダー的なポジションとなってきて仕事の全体をみながら責任者としての仕事をするようにもなります。
仕事の内容が変わることで保育士に向いていないのではないかと、保育士自体を辞めてしまいたいと考える人も多くなります。
今回は、5年目の保育士が退職を考えるとき、どのような理由があるかや、実際に辞める時に起こるトラブルについてご紹介します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ30年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
保育士の離職は5年未満が一番多い!
厚生労働省「保育士の現状と主な取組」によると、常勤保育士の経験年数別の人数は、経験年数2年未満の保育士で「15.5%」、2~4年未満の保育士で「13.3%」、4~6年未満の保育士で「11.1%」となっています。
合計すると、6年未満の保育士が全体の39.9%を占めており、現職の保育士の約4割が6年未満の保育士であることがわかります。
保育士5年目で向いてない、辞めたいと思う主な理由
保育士に向いていないと思う理由はさまざまですが、ここからもう少し詳細に5年目の保育士が辞めたいと思う理由を具体的にご紹介します。
理由1:仕事量の多さについていけない
ここ数年は保育士不足の影響もあり、保育士一人ひとりに対する仕事量が増えています。
また、5年目になるまで年次が上がるたびに立場も上がり、業務が増えるにも関わらず後輩保育士が定着しないなど、仕事をうまく後輩に引き継ぐことができない状況も生まれています。
年々増えていく仕事量の多さに、この先の将来を考えると保育士という仕事を辞めたいと考えるようになります。
理由2:性格的に向いていない
保育士の多くは子どもが好きで、その成長を支援したいという理由から保育士になっています。
しかし、実際の保育士の仕事は子どもとただ遊んでいるだけの仕事ではありません。
命の責任を請け負い、時に厳しく指導することも必要です。
また、保護者対応や事務作業など、保育以外の仕事も多くあり、イメージしていた保育士の仕事とのギャップに「性格上向いていないのでは?」と感じることが多くなり、保育士を辞めたいと感じてしまうようです。
理由3:責任のある仕事が多くなり、プレッシャーに耐えられない
5年目の保育士となると、保育園では中堅と言われることもあります。
早い方だと、クラス担任という仕事だけでなく、職務分野別リーダーという職務にキャリアアップすることもあります。
キャリアアップ自体は喜ぶことではありますが、まだ仕事に対して自信が持てず、不安を感じてプレッシャーになってしまうことがあります。
こうしたプレッシャーに耐えられなくなった場合、今後のキャリアプランに不安を感じたり、キャリアアップすること自体を怖いと感じたりしてしまう場合に退職を考えるようになります。
理由4:保護者対応が慣れない
保護者対応を苦手とする保育士は少なくありません。
日々の送迎時の短い時間で的確なコミュニケーションが求められる保護者対応は、言い方や伝え方を間違えると大きな問題に発展することもあります。
また、モンスターペアレンツと言われるクレーマーに近い保護者の存在も近年増加してきました。
周囲からは「5年目なので保護者対応も完璧にできて当たり前」というプレッシャーの中、保護者対応をしなくてはならないストレスに耐えかねる保育士も多くいます。
理由5:給料や勤務体型に不満を感じる
保育士の給料は年々上がっていますが、拘束時間や勤務時間を考慮するとまだまだ高いとは言えません。
給料が上がりにくいことや、そもそも給料が低いことが、保育士を辞める理由として非常に多いとされています。
また、シフト制ではあるものの、早朝や夕方遅くまでの勤務体制がローテーションすることにより、生活のリズムが整わないこともあります。
このような理由から、将来的にずっと保育士を続けていけるのか不安になり、退職を考えるようになる場合があります。
理由6:職場の人間関係がうまくいかない
保育士の職場は女性が多く、うまく人間関係が築けているときは良いですが、一度ギスギスし始めるとどうすることもできなくなります。
また、職員室という場は、誰かが入ってくることが少なく、いじめやパワハラなどがあった場合に発覚することがなく、閉鎖的な場所になりやすいことも人間関係を拗らせる要因の一つです。
保育士にとって、園内の人間関係は退職理由の常に上位に来る理由の一つです。
保育士自体ではなく、その保育園や保育士としての働き方に自分が合っていないだけかも?
保育士を辞めたいと考えたとき、保育士自体が向いてないのか、保育園に合っていないのかが曖昧になっている方は非常に多いです。
まずは、自分が退職をしようと思った理由について、しっかりと考えることが必要です。
例えば、人間関係がうまくいかない、給料などの労働条件への不満、仕事量の多さなどは確実に「保育園に合っていない」ということに分類され、保育園を変えることでうまくいくことがあります。
また、責任のある仕事が多くなり、プレッシャーに耐えられないなどは、そもそも担任などにならないような職種や、保育士の働き方(派遣保育士など)を探せば悩みを解消することができます。
特に派遣保育士は、保育補助などのサポート的な立場で働くことになるので、担任業務やリーダー業務が負担になって辞めたいと感じている人にとっては、肩の荷を下ろして働ける雇用形態と言えます。
派遣にあまり良いイメージを持っていない方もいると思いますが、実は保育士の場合は、給与面でも雇用面でも安定した働き方です。
給与面から見ると、確かにボーナスがある正職員のほうが年収は高いものの、月給で比較すると正職員と派遣の間にそれほど差はありません。
また、保育士は慢性的な人手不足なので、よほど問題がない限り派遣切りにあうこともありません。
このように、派遣保育士は世間のイメージとは異なり、自分らしく柔軟に安定して働けるので、「保育士の仕事は好きだけど、仕事の負担が大きいのはツラい」「もっと自分のペースで働きたい」という方にぴったりです。
もちろん、派遣保育士になったからといって、この先もずっと派遣で働かなければということはなく、「正職員に戻りたい」と思ったらいつでも戻ることができます。
派遣として働く際に登録する人材派遣会社は、派遣のみを扱っているイメージがありますが、明日香ではパート・アルバイトから正職員の求人まで幅広く取り扱っています。
専任コーディネーターが現在抱えている悩みや、今後の希望をヒアリングしながら、ライフスタイルに合わせたお仕事を提案することが可能です。
保育士に向いていないと感じたり、仕事量が負担になっていると感じたりした時は、派遣保育士という働き方を視野に入れて、自分に合った働き方や職種を探していきましょう。
5年目の保育士が辞めたいと思った場合、体調やメンタル面の余裕で転職や退職を判断しよう!
5年目になった保育士が退職を考えた場合、まずは辞めたい理由を冷静に判断しましょう。
辞める理由が「保育園を変えること」で改善することであれば、転職活動を始めてみることがおすすめです。
ただし、今の不満が他の保育園で必ずしも解決できるとは限りません。
その現実を見ることで、今の保育園の問題を冷静に考えることにもつながります。
保育士自体が向いてないのではないかと考えた時も、同じように他業種の転職を前提に活動を開始してみましょう。
転職の理由が「体調やメンタル面」にある場合は、まずは自分を大切にすることが必要です。
休職などを申し出て、休養を取ることで冷静に判断できるようにもなります。
休養を取った上で、これ以上続けることができないとなった場合は、退職の判断をするようにしましょう。
5年目の保育士が辞める一般的なフロー
5年目の保育士が退職する一般的な流れは、まず退職の意思を伝えることから始まります。
退職の意思は、法的には退職希望日の14日前までに申告をするようになっていますが、一般的には1ヶ月程度前に申告するのが良いとされています。
まずは直属の上司に退職意思を伝え、その後園長に伝えます。
園長に伝えた後に、保育園側から退職に関する書類等が発行されますので提出します。
退職日には、保険証や貸与品の返却を行い退職となります。
一緒に働く同僚などに伝える場合は、保育園側の指示に従うようにしましょう。
職場の環境などに配慮して情報の解禁日を設ける保育園もあります。
また、引き継ぎについても後任者が困ることのないように、できる限り行うことで、あなた自身の今後の成長に繋がります。
子どもたちや保護者へ退職を伝えるかどうかも保育園の方針によります。
関わりのあった方々へ直接伝えたい思いがあったとしても、今後の影響を考えて退職後にプリントで伝えるなど保育園側にも方針があります。
周囲への混乱を招かないためにも、退職についてどのように伝えるかは、園長や上司に聞いてみてから進めるようにしましょう。
5年目の保育士が辞める上でよくあるトラブルとその対処法
仕事も理解し、重要なポジションを任されるようになった5年目の保育士が「辞めたい」と考え始めると、さまざまなトラブルがあります。
具体的にどのようなトラブルがあるか、事前に知っておくことで対応も変わります。
ここからは、よくあるトラブルについて解説します。
【1】引き留めが強く、園がなかなか休職や退職に応じてくれない
人員不足に悩む保育園では、仕事を安心して任せられる保育士に辞められることは大きな痛手です。
そのため、周囲からは「辞めないでほしい」というプレッシャーがかかり、自分の意思を示すことができない状態に追い込まれることがあります。
引き留めが強く、園がなかなか休職や退職に応じてくれない場合は、労働基準監督署などの第三者機関に相談しましょう。
【2】次の職場でうまくいくかが心配
退職後、次の保育園で保育士をするにしても、別の職種につくにしても、「また同じような問題が出てしまうのでは」と心配になって、退職に踏み切れない方もいます。
慎重に判断することは大切なことですが、モヤモヤしたストレスを抱えたまま働いていると、体調やメンタルに支障が出てくることがあります。
体調やメンタルに支障が出ている場合、次の職場では紹介予定派遣など雇用形態を変更する選択もあります。
紹介予定派遣は、一定の期間を派遣社員として勤務し、実際の職場をみた上で双方の合意により、直接雇用へ変更する雇用形態です。
人材派遣会社など、転職のプロにも相談できるので、心配な場合は転職活動を一人で進めることなく、まずは転職エージェントや人材派遣会社に相談しましょう。
【3】なんとなくキャリアがもったいない気がして踏ん切りがつかない
せっかく5年間という保育士キャリアを築き、ある程度のポジションについている場合は、これまで頑張ってきた保育園を退職することにもったいなさを感じることがあります。
そして、キャリアアップのためには、転職するよりも同じ保育園で勤務し続ける方が近道かもしれません。
これからのキャリアをどのように築きたいのか、長期的な視点で考え、転職をするかどうかについて自分なりにしっかりと考えましょう。
自分自身が今後どうなりたいかを優先して考えていくことが大切です。
【4】周りに悪いと思ってなかなか踏ん切りがつかない
人員不足の保育園が多い中、自分が辞めてしまうことによって同僚保育士に負担がかかることを心配し、辞めることに決心がつかないこともあります。
しかし、「同僚保育士に迷惑がかかってしまうのでは?」という心配は、あなたにとってプラスにはなりません。
時には他人の目を気にすることなく、自分にとって優先すべきことは何かをしっかり考え、自分なりに出した結論を優先するようにしましょう。
【5】園長や上司との折り合いが悪く、なかなか相談自体ができない
退職の第一歩は、園長や上司へ退職意思を伝えることですが、そもそも人間関係が悪く、退職の意思を伝えられない、聞いてもらえない場合もあります。
その場合は、住んでいる地域の労働基準監督署にある退職相談窓口に相談してみるのがおすすめです。
退職に関するトラブルは、労働基準監督署が直接介入するわけではありません。
しかし、窓口の相談員たちは数々の退職に関する相談を受けているため、個々の状況に応じた解決手段について相談に乗ってくれます。
最近では、退職代行サービスもあり、どうしても直接交渉ができない場合は、こうしたサービスを利用することも検討してみましょう。
5年目で辞めたいと思うことはよくある!辞めたいと思ったら、まずは体調で判断して行動しよう!
保育士5年目になると、仕事の幅も増え、退職を考えることはよくあることです。
辞めたいと考えた時、すでに体調やメンタルに支障をきたしている場合は、ゆっくりと休養できる方法を探しましょう。
退職や休職などさまざまな方法があるので、思い詰める前に身体を労わることを考え、その後ゆっくり判断するようにしましょう。
心身ともに限界が来ている場合は、すぐに休養をとることが大切です。
まだ余裕があり、働き続けながら体調を整えたい場合は、派遣保育士として働くのも1つの方法です。
もし、相談したいことがあれば、まずは次の登録フォームから保育士登録をして、専任コーディネーターに今抱える悩みなどを相談してみてください。

