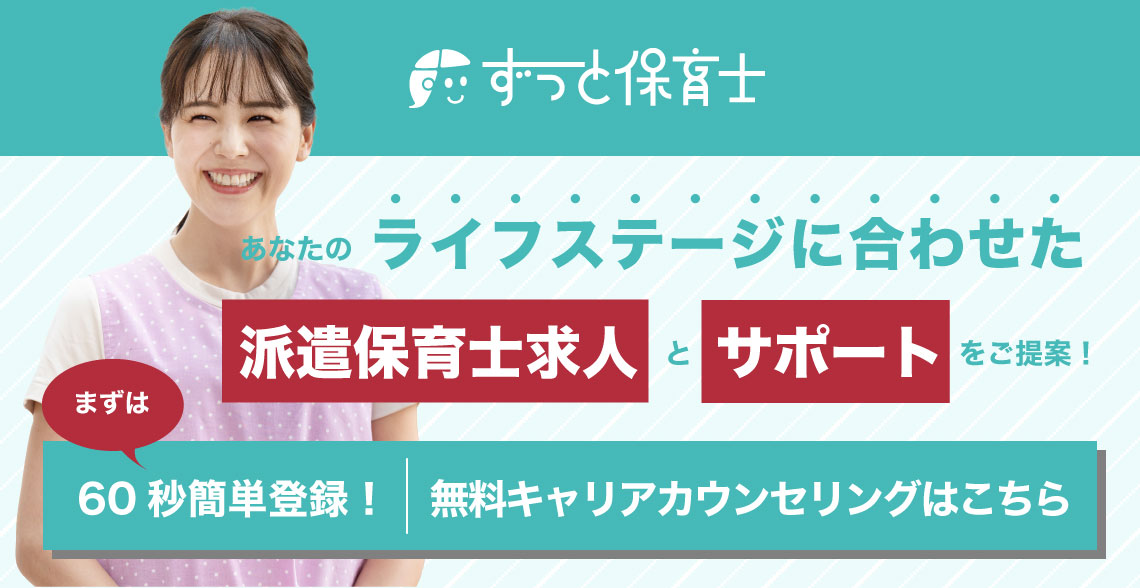派遣保育士が使える家賃補助はあるの?
2025/09/11
「派遣保育士として働きたいけど、家賃の負担が大きい」と感じたことはありませんか?
特に、一人暮らしをしている方や、上京して働くことを考えている方にとって、家賃は毎月の大きな出費です。
一般的に、派遣社員は正社員よりも福利厚生の内容が限られる傾向があります。
しかし、働き方によっては、家賃補助を受けられる場合もあるのです。
この記事では、派遣保育士がどのような形で補助の対象となるのか、家賃補助を活用した体験談、メリット・デメリットなどを解説します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
派遣保育士が家賃補助を受けられるかは派遣会社により、方法は2つある
派遣保育士が家賃補助を受ける方法は、次の2つがあります。
- ・派遣社員として派遣会社の家賃補助を使う
- ・自治体が用意する「保育士宿舎借り上げ支援事業」制度を利用する
以下から、それぞれ見ていきましょう。
派遣社員として派遣会社の家賃補助を使う
派遣保育士が会社から家賃補助を受けたい場合、福利厚生制度が整った派遣会社に登録をしましょう。
具体的には、住宅手当・社宅制度・寮制度・住宅補助金などの形で支給されるケースがあります。
これらは会社ごとに内容が異なるため、「どのような住宅関連の制度があるか」「対象者の条件はあるか」などを登録時に確認すると安心です。
なお、家賃補助は法律によって企業に義務付けられているものではなく、各派遣会社の裁量に委ねられています(労働基準法では家賃補助の支給義務は定められていません)。
また、派遣社員の場合、福利厚生の内容は派遣会社によって決まるため、家賃補助を受けられるのかは、登録する会社によって左右されます。
そのため、家賃補助を使いたい場合、登録の段階で支給の有無を確認しておきましょう。
自治体が用意する「保育士宿舎借り上げ支援事業」制度を利用する
派遣社員が使える家賃補助として、「保育士宿舎借り上げ支援事業」という制度があり、次のような条件や一例があります。
- ・受け取るための基本的な条件
- ・支援事業制度の一例
以下から、詳しく解説します。
受け取るための基本的な条件
自治体では「保育士宿舎借り上げ支援事業」という名目で家賃補助を実施しています。
この制度は、保育園等が職員のために借り上げた宿舎の賃料の一部を、自治体が保育園等に補助する仕組みです。
厚生労働省が示す「保育人材確保等支援事業実施要綱」に基づいて、自治体が独自に運用を行っているものです。
補助金が直接保育士に支給されるわけではなく、あくまで運営法人を通じて家賃負担が軽減される点に注意しましょう。
また、対象となる職員は「常勤で働いている」ことが基本条件となり、さらに「採用から10年以内」といった要件を設けている自治体も多いです。
ただし、細かい支給要件は自治体によって異なります。
そのため、条件を満たしているか事前に確認し、不安な場合は登録時に派遣会社へ相談しましょう。
支給条件は自治体によって異なる
「保育士宿舎借り上げ支援事業」の支給条件は、自治体ごとに異なります。
国の制度をベースにしているものの、運用自体は自治体に委ねられているからです。
たとえば「常勤で働いている」といった条件では、派遣社員でも支給対象になっている自治体もあれば、直接雇用のみとされている可能性もあります。
このように、一概に「条件を満たしている」とは判断できないため、派遣会社に確認しましょう。
支援事業制度の一例
支援事業制度を行っている一例として、世田谷区(東京都)を見ていきましょう。
世田谷区では、支給条件として常勤職員であることや、指定の宿舎に居住することなどが挙げられています。
また、常勤職員以外の働き方であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は、「常勤職員に準ずる勤務形態」として制度の対象となることがあります。
支給額は、最大月額82,000円となっており、7/8は補助金による負担、1/8は運営事業者の負担です。
区内の認可保育園等に勤務する常勤保育従事職員が、保育運営事業者が賃借する住宅に入居する場合、82,000円を補助基準上限額として、保育運営事業者に補助を行います。(月額賃料82,000円で、居住する保育士に負担を求めない場合、事業者負担10,250円が生じます。)
敷金、仲介手数料など「預かり金」のような扱いになるものは、支給の対象外です。
このように、上手に補助金を利用できれば、生活費を抑えられます。
家賃補助のある保育士派遣会社の探し方
家賃補助のある派遣会社の探し方としては、次のような方法があります。
- ・どのようなサポートを受けられるか?で探す
- ・どのような求人を取り扱っているか?を探す
以下から、順番に見ていきましょう。
どのようなサポートを受けられるか?で探す
家賃補助や手続きのサポートの有無は、派遣会社によって異なります。
たとえば、求人票に家賃補助について明記されていなくても支給されるケースもありますが、これは稀なケースであり、基本的には求人票や派遣会社の福利厚生制度案内で確認するのが良いでしょう。
また、求人票に「家賃補助あり」と記載されていても、勤務地や勤務日数などの条件が付く場合があるため、事前に詳細を確認することが大切です。
さらに、派遣会社の家賃補助があるのかに加え、申請手続きのサポートはあるのか、通勤時間を配慮してくれるのかなどの点を意識するのもポイントです。
そのため、「住まいに関すること全般」としてサポートがあるかを確認し、登録する派遣会社を決めましょう。
どのような求人を取り扱っているか?を探す
派遣会社を決めるときには、どのような求人を取り扱っているかで探しましょう。
派遣会社によって、得意なエリアであったり、職種であったりは異なるからです。
たとえば、都市部に近い求人を多く取り扱っている会社であれば、「保育士宿舎借り上げ支援事業」の家賃補助の対象となる可能性があります。
都市部では保育園のニーズが高く、自治体としても保育士の確保に力を入れているケースが多くあります。
厚生労働省によると、令和6年4月の待機児童数は2,567人と、依然高い状況です。
そのため、人材確保の必要性が高い地域では、自治体が家賃補助などの手厚い支援策を行う傾向があり、派遣保育士もその対象に含まれる場合があります。
このように、どのような求人を取り扱っているかによって、家賃補助を受けられるかが異なります。
派遣保育士の家賃補助でよくある質問
派遣保育士のよくある質問として、次の内容が挙げられます。
- ・保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するメリットは?
- ・保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するデメリットは?
- ・家賃補助以外にも受け取れる補助はあるの?
以下から、順番に解説します。
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するメリットは?
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を使うと家賃の負担を減らせる点が、最大のメリットです。
家賃は月々の支出の中で大きな割合を占める一方で、給料の3分の1以内に抑えるのが良いとされています。
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用すれば、支出のバランスを保ちながら派遣保育士として働けます。
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するデメリットは?
派遣保育士が、保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するデメリットとしては、正社員に比べて条件を満たしにくいという点があります。
「常勤の保育士」を対象とした制度なため、派遣保育士のような有期雇用のスタッフまで対象になるかが、自治体によって異なるためです。
このように、「条件を満たしにくい」「支給対象となっているかわかりにくい」といった点がデメリットといえます。
家賃補助以外にも受け取れる補助はあるの?
派遣保育士が受け取れるのは家賃補助だけでなく、条件を満たせば「処遇改善手当」も支給対象となります。
処遇改善手当は、厚生労働省の指導に基づき、保育施設が国から加算を受け、その資金を使って職員の賃金を改善する仕組みです。
加算にはⅠ・Ⅱ・Ⅲがあり、それぞれ対象や条件が異なります。
たとえば、処遇改善等加算Ⅰでは、施設が賃金改善計画を策定し、キャリアパス要件(例:職務分野別リーダーや専門リーダーなどの配置)を満たすことで支給対象となります。
派遣保育士の場合「処遇改善手当Ⅰ」の対象となっており、金額としては、月1〜4万円前後の計算になります。
ただし、処遇改善手当Ⅰの金額は、保育園の給与体系や職務内容によって異なり、一律に月1〜4万円が支給されるわけではありません。
また、処遇改善手当Ⅰの対象には「経験年数が3年以上」などの条件があり、派遣職員であっても勤務実績やキャリアによって対象となる場合があります。
支給金額や分配に関しても保育園によって異なるため、そのままの金額で支払われるわけではないことに注意しましょう。
派遣会社に登録する際の注意点は?
家賃補助や補助金を受けたい場合、派遣会社に登録する前に福利厚生の内容を確認しましょう。
派遣会社の取り扱い求人やサポート体制によって、どのような場所や条件で働けるかが異なるためです。
たとえば、「家賃補助は受けられたけど、保育園の方針や人間関係が合わず、体調を崩してしまった」となってしまっては、本末転倒です。
そのため、補助や求人の条件だけに目を向けずに、ライフスタイルに合わせたさまざまな求人があるか、親身になってくれるかなどにも注意しましょう。
派遣保育士でも家賃補助はもらえる!納得の行く条件で求人を探そう
この記事では、派遣保育士でも家賃補助は受けられるのかという内容をご紹介しました。
また、わたしたち明日香が運営している「ずっと保育士」では、雇用形態・働く場所など条件を絞って求人を探せます。
福利厚生の充実した求人や、ライフステージに合わせた働き方などで、保育士の皆さまをサポートしています。
もし、ご興味があればこちらからご確認ください。
カテゴリ
保育士キャリア
ずっと保育士は、保育のお仕事を始めたい、転職・復職したい方にライフステージにあった保育のお仕事をご紹介したい。そして保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援し続けたい、という想いでサービスを運営しています。
60秒で完了!無料会員登録をする
「派遣保育士として働きたいけど、家賃の負担が大きい」と感じたことはありませんか?
特に、一人暮らしをしている方や、上京して働くことを考えている方にとって、家賃は毎月の大きな出費です。
一般的に、派遣社員は正社員よりも福利厚生の内容が限られる傾向があります。
しかし、働き方によっては、家賃補助を受けられる場合もあるのです。
この記事では、派遣保育士がどのような形で補助の対象となるのか、家賃補助を活用した体験談、メリット・デメリットなどを解説します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
派遣保育士が家賃補助を受けられるかは派遣会社により、方法は2つある
派遣保育士が家賃補助を受ける方法は、次の2つがあります。
- ・派遣社員として派遣会社の家賃補助を使う
- ・自治体が用意する「保育士宿舎借り上げ支援事業」制度を利用する
以下から、それぞれ見ていきましょう。
派遣社員として派遣会社の家賃補助を使う
派遣保育士が会社から家賃補助を受けたい場合、福利厚生制度が整った派遣会社に登録をしましょう。
具体的には、住宅手当・社宅制度・寮制度・住宅補助金などの形で支給されるケースがあります。
これらは会社ごとに内容が異なるため、「どのような住宅関連の制度があるか」「対象者の条件はあるか」などを登録時に確認すると安心です。
なお、家賃補助は法律によって企業に義務付けられているものではなく、各派遣会社の裁量に委ねられています(労働基準法では家賃補助の支給義務は定められていません)。
また、派遣社員の場合、福利厚生の内容は派遣会社によって決まるため、家賃補助を受けられるのかは、登録する会社によって左右されます。
そのため、家賃補助を使いたい場合、登録の段階で支給の有無を確認しておきましょう。
自治体が用意する「保育士宿舎借り上げ支援事業」制度を利用する
派遣社員が使える家賃補助として、「保育士宿舎借り上げ支援事業」という制度があり、次のような条件や一例があります。
- ・受け取るための基本的な条件
- ・支援事業制度の一例
以下から、詳しく解説します。
受け取るための基本的な条件
自治体では「保育士宿舎借り上げ支援事業」という名目で家賃補助を実施しています。
この制度は、保育園等が職員のために借り上げた宿舎の賃料の一部を、自治体が保育園等に補助する仕組みです。
厚生労働省が示す「保育人材確保等支援事業実施要綱」に基づいて、自治体が独自に運用を行っているものです。
補助金が直接保育士に支給されるわけではなく、あくまで運営法人を通じて家賃負担が軽減される点に注意しましょう。
また、対象となる職員は「常勤で働いている」ことが基本条件となり、さらに「採用から10年以内」といった要件を設けている自治体も多いです。
ただし、細かい支給要件は自治体によって異なります。
そのため、条件を満たしているか事前に確認し、不安な場合は登録時に派遣会社へ相談しましょう。
支給条件は自治体によって異なる
「保育士宿舎借り上げ支援事業」の支給条件は、自治体ごとに異なります。
国の制度をベースにしているものの、運用自体は自治体に委ねられているからです。
たとえば「常勤で働いている」といった条件では、派遣社員でも支給対象になっている自治体もあれば、直接雇用のみとされている可能性もあります。
このように、一概に「条件を満たしている」とは判断できないため、派遣会社に確認しましょう。
支援事業制度の一例
支援事業制度を行っている一例として、世田谷区(東京都)を見ていきましょう。
世田谷区では、支給条件として常勤職員であることや、指定の宿舎に居住することなどが挙げられています。
また、常勤職員以外の働き方であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は、「常勤職員に準ずる勤務形態」として制度の対象となることがあります。
支給額は、最大月額82,000円となっており、7/8は補助金による負担、1/8は運営事業者の負担です。
区内の認可保育園等に勤務する常勤保育従事職員が、保育運営事業者が賃借する住宅に入居する場合、82,000円を補助基準上限額として、保育運営事業者に補助を行います。(月額賃料82,000円で、居住する保育士に負担を求めない場合、事業者負担10,250円が生じます。)
敷金、仲介手数料など「預かり金」のような扱いになるものは、支給の対象外です。
このように、上手に補助金を利用できれば、生活費を抑えられます。
家賃補助のある保育士派遣会社の探し方
家賃補助のある派遣会社の探し方としては、次のような方法があります。
- ・どのようなサポートを受けられるか?で探す
- ・どのような求人を取り扱っているか?を探す
以下から、順番に見ていきましょう。
どのようなサポートを受けられるか?で探す
家賃補助や手続きのサポートの有無は、派遣会社によって異なります。
たとえば、求人票に家賃補助について明記されていなくても支給されるケースもありますが、これは稀なケースであり、基本的には求人票や派遣会社の福利厚生制度案内で確認するのが良いでしょう。
また、求人票に「家賃補助あり」と記載されていても、勤務地や勤務日数などの条件が付く場合があるため、事前に詳細を確認することが大切です。
さらに、派遣会社の家賃補助があるのかに加え、申請手続きのサポートはあるのか、通勤時間を配慮してくれるのかなどの点を意識するのもポイントです。
そのため、「住まいに関すること全般」としてサポートがあるかを確認し、登録する派遣会社を決めましょう。
どのような求人を取り扱っているか?を探す
派遣会社を決めるときには、どのような求人を取り扱っているかで探しましょう。
派遣会社によって、得意なエリアであったり、職種であったりは異なるからです。
たとえば、都市部に近い求人を多く取り扱っている会社であれば、「保育士宿舎借り上げ支援事業」の家賃補助の対象となる可能性があります。
都市部では保育園のニーズが高く、自治体としても保育士の確保に力を入れているケースが多くあります。
厚生労働省によると、令和6年4月の待機児童数は2,567人と、依然高い状況です。
そのため、人材確保の必要性が高い地域では、自治体が家賃補助などの手厚い支援策を行う傾向があり、派遣保育士もその対象に含まれる場合があります。
このように、どのような求人を取り扱っているかによって、家賃補助を受けられるかが異なります。
派遣保育士の家賃補助でよくある質問
派遣保育士のよくある質問として、次の内容が挙げられます。
- ・保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するメリットは?
- ・保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するデメリットは?
- ・家賃補助以外にも受け取れる補助はあるの?
以下から、順番に解説します。
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するメリットは?
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を使うと家賃の負担を減らせる点が、最大のメリットです。
家賃は月々の支出の中で大きな割合を占める一方で、給料の3分の1以内に抑えるのが良いとされています。
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用すれば、支出のバランスを保ちながら派遣保育士として働けます。
保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するデメリットは?
派遣保育士が、保育士宿舎借り上げ支援事業制度を利用するデメリットとしては、正社員に比べて条件を満たしにくいという点があります。
「常勤の保育士」を対象とした制度なため、派遣保育士のような有期雇用のスタッフまで対象になるかが、自治体によって異なるためです。
このように、「条件を満たしにくい」「支給対象となっているかわかりにくい」といった点がデメリットといえます。
家賃補助以外にも受け取れる補助はあるの?
派遣保育士が受け取れるのは家賃補助だけでなく、条件を満たせば「処遇改善手当」も支給対象となります。
処遇改善手当は、厚生労働省の指導に基づき、保育施設が国から加算を受け、その資金を使って職員の賃金を改善する仕組みです。
加算にはⅠ・Ⅱ・Ⅲがあり、それぞれ対象や条件が異なります。
たとえば、処遇改善等加算Ⅰでは、施設が賃金改善計画を策定し、キャリアパス要件(例:職務分野別リーダーや専門リーダーなどの配置)を満たすことで支給対象となります。
派遣保育士の場合「処遇改善手当Ⅰ」の対象となっており、金額としては、月1〜4万円前後の計算になります。
ただし、処遇改善手当Ⅰの金額は、保育園の給与体系や職務内容によって異なり、一律に月1〜4万円が支給されるわけではありません。
また、処遇改善手当Ⅰの対象には「経験年数が3年以上」などの条件があり、派遣職員であっても勤務実績やキャリアによって対象となる場合があります。
支給金額や分配に関しても保育園によって異なるため、そのままの金額で支払われるわけではないことに注意しましょう。
派遣会社に登録する際の注意点は?
家賃補助や補助金を受けたい場合、派遣会社に登録する前に福利厚生の内容を確認しましょう。
派遣会社の取り扱い求人やサポート体制によって、どのような場所や条件で働けるかが異なるためです。
たとえば、「家賃補助は受けられたけど、保育園の方針や人間関係が合わず、体調を崩してしまった」となってしまっては、本末転倒です。
そのため、補助や求人の条件だけに目を向けずに、ライフスタイルに合わせたさまざまな求人があるか、親身になってくれるかなどにも注意しましょう。
派遣保育士でも家賃補助はもらえる!納得の行く条件で求人を探そう
この記事では、派遣保育士でも家賃補助は受けられるのかという内容をご紹介しました。
また、わたしたち明日香が運営している「ずっと保育士」では、雇用形態・働く場所など条件を絞って求人を探せます。
福利厚生の充実した求人や、ライフステージに合わせた働き方などで、保育士の皆さまをサポートしています。
もし、ご興味があればこちらからご確認ください。