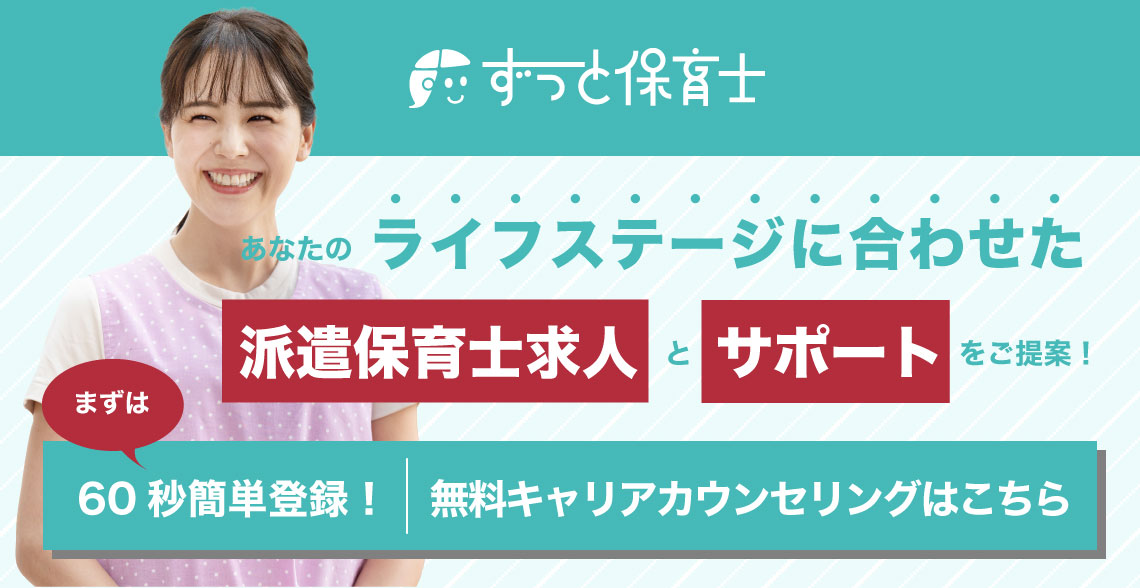派遣保育士でも産休は取れる?条件・期間・手続き・復帰までを徹底解説
2025/09/11
派遣保育士という立場で働いていると、「産休ってちゃんと取れるのかな?」「派遣だから制度の対象外かも…」と不安に感じている方も少なくないと思います。
妊娠や出産が見えてきたとき、自分の働き方のまま休めるのか、復帰できるのかがわからず、誰にも相談できずに悩んでしまうこともあるでしょう。
しかし、産休は労働基準法第65条で定められた制度です。
同条では「産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間の休業」を女性労働者に認めており、この間の就業を原則禁止としています。
正社員だけでなく、派遣保育士を含むすべての雇用形態に適用されており、正しく条件を満たしていれば取得することができます。
この記事では、派遣保育士が産休を取るための条件や取得できる期間、手続きの流れ、復帰後の働き方までを、わかりやすく解説していきます。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
派遣保育士でも産休は取得できる
産前産後休業は、労働基準法第65条に基づいて定められた制度であり、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
正社員やパート、契約社員、そして派遣社員も例外でないため「派遣だから産休が取れないのでは」と心配する必要はありません。
一定の条件を満たしていれば、派遣保育士も制度に基づき、安心して休業を取得できます。
厚生労働省が2015年度に実施した「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査」(実施:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)では、非正社員のうち約27.5%が実際に産休を取得しており、平均取得期間は正社員とほぼ同等の89日という結果が出ています。
また、制度の存在を知りながら利用できなかった非正社員が約3割存在。
つまり、制度自体は派遣社員を含むすべての労働者に対して機能していることが伺えます。
ただし、産休中の給与の支払い有無や、休業後の復帰先については、派遣会社の規定や契約状況によって異なる場合も。
取得のタイミングが近づいたら、早めに派遣会社と相談し、自分の働き方に合わせた準備を進めておくと安心です。
派遣保育士が産休を取るための条件
ここでは、派遣保育士が産休を取得するために必要な条件について解説します。
- ・産休開始日に派遣会社との雇用契約が残っていること
- ・社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
産休開始日に派遣会社との雇用契約が残っていること
派遣保育士が産休を取得するには、実務上、産休開始予定日の時点で派遣会社との雇用契約が継続していることが重要です。
法律上は雇用形態を問わず取得が可能ですが、契約が終了している場合は給与や出産手当金の対象とならない可能性があるため、注意が必要です。
ただし、契約期間中に産休開始日が含まれていれば取得は可能です。
さらに、健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合など、退職日までに支給要件を満たしていれば、退職後も出産手当金が継続して支給される特例(健康保険法第102条)があります。
ご自身の状況によって扱いが異なるため、派遣会社や加入している健康保険組合に必ず確認しておきましょう。
契約の終了時期や更新予定によっては取得可否が分かれるため、早めに派遣会社へ相談し、必要に応じて契約更新を確認しておくことが安心につながります。
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
産休の取得にあたって、社会保険の加入は必須ではありません。
しかし、出産手当金の受給を希望する場合は、健康保険に加入していることが条件となります。
出産手当金は、産休中に給与が支払われない期間の生活を支えるために、健康保険の被保険者に対して支給される制度です。
標準報酬日額の約3分の2が、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの最大98日間支給されます(参考:協会けんぽ|出産手当金について)。
制度を正しく活用するためにも、出産手当金の支給要件である「健康保険への継続加入」や「支給開始日以前12か月以上の被保険者期間があること」など、自身の保険加入状況を事前に確認しておきましょう。
派遣保育士の産前休業は出産予定日の6週間前から取得できる
産休は「産前休業」と「産後休業」に分かれており、産前休業は出産予定日の6週間前から取得できます。
産前休業を取得するには、医師の診断書など出産予定日が記載された書類を派遣会社へ提出し、正式な申請を行う必要があります。
正社員やパートと同様に、派遣保育士も同じ制度が適用されるため、安心して休みに入りましょう。
また、多胎妊娠(双子以上)の場合は、14週間前から取得できると労働基準法で定められています。
休業のタイミングは個人の体調や就業状況にもよるため、早めに派遣会社と相談し、無理のないスケジュールを立てることが大切です。
派遣保育士の産後休業は出産の翌日から8週間取得できる
出産の翌日から8週間は、労働基準法第65条第2項により、産後休業の取得が義務づけられています。
ただし、同条第3項により、産後6週間を経過し、本人が希望し医師が認めた場合は、就業することも例外的に認められています。
この期間は体の回復と赤ちゃんとの生活に集中するための大切な時間とされており、原則として就業は禁止されています。
派遣保育士も例外ではなく、法律に基づいて休業を取得することができます。
ただし、産後6週間を経過し、本人が希望し、かつ医師が認めた場合に限り、就業することも可能です。
実際の復帰タイミングは体調や育児の状況にもよるため、無理のない計画を立てましょう。
派遣保育士が産休を取得する手続きと申請の流れ
ここでは、派遣保育士が産休を取得する際に必要な手続きや、実際の進め方について解説します。
- ・派遣会社に産休取得の意思を伝える
- ・派遣先には安定期以降で早めに報告する
- ・必要書類を準備して派遣会社に提出する
それぞれ、順番に確認していきましょう。
①派遣会社に産休取得の意思を伝える
派遣保育士は、派遣会社と雇用契約を結んで働いているため、産休の取得についてはまず派遣会社に相談しましょう。
法律上、産休はすべての労働者に認められた権利です。
しかし、実際に休業に入るためには、就業先や契約内容の調整が必要になる場合もあります。
妊娠が分かった時点で、できるだけ早めに派遣会社へ報告してください。
必要な書類や今後の流れについても具体的に説明してもらえるため、不安や疑問を事前に解消しやすくなります。
②派遣先には安定期以降で早めに報告する
派遣保育士の場合、雇用主は派遣会社ですが、日々の勤務先である保育園とも連携が必要です。
法律上は派遣先へ直接報告する義務はありませんが、引き継ぎや人員調整の関係から、現場への配慮として報告は早めに行うのが望ましいとされています。
一般的には、安定期(妊娠5ヶ月ごろ)に入ってから産休開始の1〜2ヶ月前までに、派遣会社を通じて伝えるケースが多いです。
事前に派遣会社と相談しながら、タイミングを調整しておきましょう。
③必要書類を準備して派遣会社に提出する
産休を取得する際には、派遣会社から指定された書類を提出する必要があります。
一般的には、母子健康手帳の写しや出産予定日が記載された医師の診断書などが求められます。
これらの書類は、産休の正式な申請を行う際に必要となるため、準備が整い次第、早めに提出するのが安心です。
書類に不備があると手続きがスムーズに進まない可能性もあるため、記入内容や提出期限を確認したうえで、余裕を持って対応しておきましょう。
派遣保育士の産休後の働き方と復帰の流れ
派遣保育士が産休を終えたあと、どのように職場復帰を進めていくのかの流れとして、次が挙げられます。
- ・産休後の復帰は派遣会社と相談して決まる
- ・同じ派遣先に戻れる場合と戻れない場合がある
- ・復帰支援やサポート制度を用意している派遣会社もある
それぞれのポイントについて、順に見ていきましょう。
産休後の復帰は派遣会社と相談して決まる
産休後の復職に関しては、出産前から派遣会社と具体的に相談しておくことが重要です。
希望する復帰時期や勤務日数、働き方(時短やフルタイム)などを事前に伝えておくことで、復帰後のミスマッチを防ぎやすくなります。
また、家庭との両立や保育方針の希望がある場合も、遠慮なく伝えることで、自分に合った勤務先を紹介してもらいやすくなります。
復帰後の不安を減らすためにも、早めの準備と情報共有がポイントです。
同じ派遣先に戻れる場合と戻れない場合がある
産休後に元の派遣先へ戻れるかどうかは、派遣先の受け入れ体制や契約状況によって異なります。
園側が継続して受け入れを希望し、かつ派遣会社との契約が続いている場合は、同じ職場に復帰できるケースもあります。
一方で、既に別の人材で補充されていたり、配置や勤務条件が合わなかったりする場合は、別の勤務先を紹介されることもあります。
復帰先にこだわりがある場合は、早めに希望を伝え、調整できるよう派遣会社と連携を取ることが大切です。
復帰支援やサポート制度を用意している派遣会社もある
産休後の復職にあたり、サポート体制を整えている派遣会社もあります。
たとえば、復帰時期の相談や勤務条件のすり合わせを行う面談、希望条件の再ヒアリング、勤務先との調整サポートなどがその一例です。
中には、出産や育児に関する不安を相談できる窓口や、段階的な復帰を支援する制度を用意している会社もあるので選ぶ際の判断材料にするといいでしょう。
派遣会社ごとに内容は異なるため、復帰を見据えて早い段階から制度の有無やサポート内容を確認しておくと安心です。
派遣保育士でも産休は取得できる!正しい知識で安心して準備を進めよう
ここまで、派遣保育士の産休について解説しました。
派遣保育士であっても、労働基準法に基づいて産休を取得する権利は保障されています。
制度の対象になるためには、産休開始時点での雇用契約や社会保険の加入状況など、いくつかの条件を満たしている必要があります。
取得までの手続きや復帰後の働き方についても、派遣会社と連携して進めていけば、無理ないかたちでの育児と仕事の両立が可能です。
出産後も自分らしく働き続けるために、制度を正しく理解し、早めの準備を心がけましょう。
産休や復職に関する不安がある方は、「ずっと保育士」へご相談ください。
産休制度の説明や復帰に向けたサポートまで、専任のコーディネーターが丁寧に対応します。
カテゴリ
保育士キャリア
ずっと保育士は、保育のお仕事を始めたい、転職・復職したい方にライフステージにあった保育のお仕事をご紹介したい。そして保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援し続けたい、という想いでサービスを運営しています。
60秒で完了!無料会員登録をする
派遣保育士という立場で働いていると、「産休ってちゃんと取れるのかな?」「派遣だから制度の対象外かも…」と不安に感じている方も少なくないと思います。
妊娠や出産が見えてきたとき、自分の働き方のまま休めるのか、復帰できるのかがわからず、誰にも相談できずに悩んでしまうこともあるでしょう。
しかし、産休は労働基準法第65条で定められた制度です。
同条では「産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間の休業」を女性労働者に認めており、この間の就業を原則禁止としています。
正社員だけでなく、派遣保育士を含むすべての雇用形態に適用されており、正しく条件を満たしていれば取得することができます。
この記事では、派遣保育士が産休を取るための条件や取得できる期間、手続きの流れ、復帰後の働き方までを、わかりやすく解説していきます。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
派遣保育士でも産休は取得できる
産前産後休業は、労働基準法第65条に基づいて定められた制度であり、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
正社員やパート、契約社員、そして派遣社員も例外でないため「派遣だから産休が取れないのでは」と心配する必要はありません。
一定の条件を満たしていれば、派遣保育士も制度に基づき、安心して休業を取得できます。
厚生労働省が2015年度に実施した「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査」(実施:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)では、非正社員のうち約27.5%が実際に産休を取得しており、平均取得期間は正社員とほぼ同等の89日という結果が出ています。
また、制度の存在を知りながら利用できなかった非正社員が約3割存在。
つまり、制度自体は派遣社員を含むすべての労働者に対して機能していることが伺えます。
ただし、産休中の給与の支払い有無や、休業後の復帰先については、派遣会社の規定や契約状況によって異なる場合も。
取得のタイミングが近づいたら、早めに派遣会社と相談し、自分の働き方に合わせた準備を進めておくと安心です。
派遣保育士が産休を取るための条件
ここでは、派遣保育士が産休を取得するために必要な条件について解説します。
- ・産休開始日に派遣会社との雇用契約が残っていること
- ・社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
産休開始日に派遣会社との雇用契約が残っていること
派遣保育士が産休を取得するには、実務上、産休開始予定日の時点で派遣会社との雇用契約が継続していることが重要です。
法律上は雇用形態を問わず取得が可能ですが、契約が終了している場合は給与や出産手当金の対象とならない可能性があるため、注意が必要です。
ただし、契約期間中に産休開始日が含まれていれば取得は可能です。
さらに、健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合など、退職日までに支給要件を満たしていれば、退職後も出産手当金が継続して支給される特例(健康保険法第102条)があります。
ご自身の状況によって扱いが異なるため、派遣会社や加入している健康保険組合に必ず確認しておきましょう。
契約の終了時期や更新予定によっては取得可否が分かれるため、早めに派遣会社へ相談し、必要に応じて契約更新を確認しておくことが安心につながります。
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していること
産休の取得にあたって、社会保険の加入は必須ではありません。
しかし、出産手当金の受給を希望する場合は、健康保険に加入していることが条件となります。
出産手当金は、産休中に給与が支払われない期間の生活を支えるために、健康保険の被保険者に対して支給される制度です。
標準報酬日額の約3分の2が、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの最大98日間支給されます(参考:協会けんぽ|出産手当金について)。
制度を正しく活用するためにも、出産手当金の支給要件である「健康保険への継続加入」や「支給開始日以前12か月以上の被保険者期間があること」など、自身の保険加入状況を事前に確認しておきましょう。
派遣保育士の産前休業は出産予定日の6週間前から取得できる
産休は「産前休業」と「産後休業」に分かれており、産前休業は出産予定日の6週間前から取得できます。
産前休業を取得するには、医師の診断書など出産予定日が記載された書類を派遣会社へ提出し、正式な申請を行う必要があります。
正社員やパートと同様に、派遣保育士も同じ制度が適用されるため、安心して休みに入りましょう。
また、多胎妊娠(双子以上)の場合は、14週間前から取得できると労働基準法で定められています。
休業のタイミングは個人の体調や就業状況にもよるため、早めに派遣会社と相談し、無理のないスケジュールを立てることが大切です。
派遣保育士の産後休業は出産の翌日から8週間取得できる
出産の翌日から8週間は、労働基準法第65条第2項により、産後休業の取得が義務づけられています。
ただし、同条第3項により、産後6週間を経過し、本人が希望し医師が認めた場合は、就業することも例外的に認められています。
この期間は体の回復と赤ちゃんとの生活に集中するための大切な時間とされており、原則として就業は禁止されています。
派遣保育士も例外ではなく、法律に基づいて休業を取得することができます。
ただし、産後6週間を経過し、本人が希望し、かつ医師が認めた場合に限り、就業することも可能です。
実際の復帰タイミングは体調や育児の状況にもよるため、無理のない計画を立てましょう。
派遣保育士が産休を取得する手続きと申請の流れ
ここでは、派遣保育士が産休を取得する際に必要な手続きや、実際の進め方について解説します。
- ・派遣会社に産休取得の意思を伝える
- ・派遣先には安定期以降で早めに報告する
- ・必要書類を準備して派遣会社に提出する
それぞれ、順番に確認していきましょう。
①派遣会社に産休取得の意思を伝える
派遣保育士は、派遣会社と雇用契約を結んで働いているため、産休の取得についてはまず派遣会社に相談しましょう。
法律上、産休はすべての労働者に認められた権利です。
しかし、実際に休業に入るためには、就業先や契約内容の調整が必要になる場合もあります。
妊娠が分かった時点で、できるだけ早めに派遣会社へ報告してください。
必要な書類や今後の流れについても具体的に説明してもらえるため、不安や疑問を事前に解消しやすくなります。
②派遣先には安定期以降で早めに報告する
派遣保育士の場合、雇用主は派遣会社ですが、日々の勤務先である保育園とも連携が必要です。
法律上は派遣先へ直接報告する義務はありませんが、引き継ぎや人員調整の関係から、現場への配慮として報告は早めに行うのが望ましいとされています。
一般的には、安定期(妊娠5ヶ月ごろ)に入ってから産休開始の1〜2ヶ月前までに、派遣会社を通じて伝えるケースが多いです。
事前に派遣会社と相談しながら、タイミングを調整しておきましょう。
③必要書類を準備して派遣会社に提出する
産休を取得する際には、派遣会社から指定された書類を提出する必要があります。
一般的には、母子健康手帳の写しや出産予定日が記載された医師の診断書などが求められます。
これらの書類は、産休の正式な申請を行う際に必要となるため、準備が整い次第、早めに提出するのが安心です。
書類に不備があると手続きがスムーズに進まない可能性もあるため、記入内容や提出期限を確認したうえで、余裕を持って対応しておきましょう。
派遣保育士の産休後の働き方と復帰の流れ
派遣保育士が産休を終えたあと、どのように職場復帰を進めていくのかの流れとして、次が挙げられます。
- ・産休後の復帰は派遣会社と相談して決まる
- ・同じ派遣先に戻れる場合と戻れない場合がある
- ・復帰支援やサポート制度を用意している派遣会社もある
それぞれのポイントについて、順に見ていきましょう。
産休後の復帰は派遣会社と相談して決まる
産休後の復職に関しては、出産前から派遣会社と具体的に相談しておくことが重要です。
希望する復帰時期や勤務日数、働き方(時短やフルタイム)などを事前に伝えておくことで、復帰後のミスマッチを防ぎやすくなります。
また、家庭との両立や保育方針の希望がある場合も、遠慮なく伝えることで、自分に合った勤務先を紹介してもらいやすくなります。
復帰後の不安を減らすためにも、早めの準備と情報共有がポイントです。
同じ派遣先に戻れる場合と戻れない場合がある
産休後に元の派遣先へ戻れるかどうかは、派遣先の受け入れ体制や契約状況によって異なります。
園側が継続して受け入れを希望し、かつ派遣会社との契約が続いている場合は、同じ職場に復帰できるケースもあります。
一方で、既に別の人材で補充されていたり、配置や勤務条件が合わなかったりする場合は、別の勤務先を紹介されることもあります。
復帰先にこだわりがある場合は、早めに希望を伝え、調整できるよう派遣会社と連携を取ることが大切です。
復帰支援やサポート制度を用意している派遣会社もある
産休後の復職にあたり、サポート体制を整えている派遣会社もあります。
たとえば、復帰時期の相談や勤務条件のすり合わせを行う面談、希望条件の再ヒアリング、勤務先との調整サポートなどがその一例です。
中には、出産や育児に関する不安を相談できる窓口や、段階的な復帰を支援する制度を用意している会社もあるので選ぶ際の判断材料にするといいでしょう。
派遣会社ごとに内容は異なるため、復帰を見据えて早い段階から制度の有無やサポート内容を確認しておくと安心です。
派遣保育士でも産休は取得できる!正しい知識で安心して準備を進めよう
ここまで、派遣保育士の産休について解説しました。
派遣保育士であっても、労働基準法に基づいて産休を取得する権利は保障されています。
制度の対象になるためには、産休開始時点での雇用契約や社会保険の加入状況など、いくつかの条件を満たしている必要があります。
取得までの手続きや復帰後の働き方についても、派遣会社と連携して進めていけば、無理ないかたちでの育児と仕事の両立が可能です。
出産後も自分らしく働き続けるために、制度を正しく理解し、早めの準備を心がけましょう。
産休や復職に関する不安がある方は、「ずっと保育士」へご相談ください。
産休制度の説明や復帰に向けたサポートまで、専任のコーディネーターが丁寧に対応します。