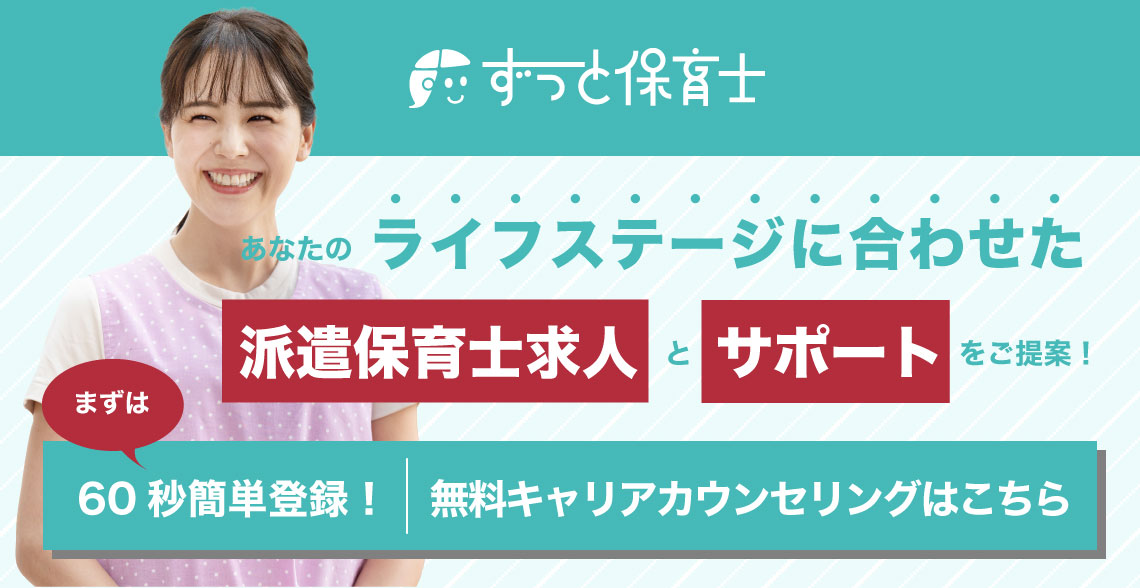派遣保育士でも育休は取得できる?条件や流れを徹底解説!
2025/09/11
現在、派遣保育士として働いている方や、これから派遣で働くことを考えている方にとっては、「育休は取れるの?」と不安になることもありますよね。
保育の仕事自体にやりがいを感じている一方で、子育てや体調のことを考えると、正社員としてのフルタイム勤務は不安という方も多くいます。
この記事では、派遣保育士でも育休を取れるのか、取得の流れや注意点、よくある質問とその答えについて、解説します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
【結論】派遣保育士でも育休は取得できる
結論からいうと、いくつかの条件を満たせば、派遣保育士でも育休を取得することは可能です。
育休は「取得時の職場で継続的に雇用されていること」が前提です。
育児・介護休業法第5条において「1年以上の雇用見込みがあること」とされており、派遣でもこれを満たせば対象になります。
そのため、育休取得時に働いていた派遣会社で働き続ける予定があるかどうかが重要なポイントになります。
たとえば、これまでに契約の更新実績があったり、派遣会社側が今後も契約を更新する意向を示している場合は、「継続雇用」の条件を満たすと判断される可能性があるでしょう。
ここでいう、「育休取得時の職場」は、正社員であれば雇用先の保育園、派遣社員であれば登録している派遣会社となります。
派遣会社の対応によっては、サポート体制や取得しやすさに差が出ることもあるため、事前に対応範囲などを確認しましょう。
派遣保育士が育休を取得する流れ
派遣保育士が育休を取得する際の手続きとして、次のような流れがあります。
- ・育休取得の条件を満たしているかを確認する
- ・育休取得の手続きをする
以下から、順番に見ていきましょう。
育休取得の条件を満たしているかを確認する
派遣には仕事があるときにだけ契約を結ぶ「登録型」と、派遣会社の正社員として継続雇用を前提とした「常用型」の種類があり、育休取得時の扱いが異なります。
派遣保育士が育休を取得する際には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、育児・介護休業法)で決められた条件を満たしている必要があります。
具体的には、育児・介護休業法第5条により「子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に契約が終了しない」という条件です。
たとえば、登録型派遣では、子どもが1歳6ヶ月になる前に派遣社員としての契約の終了が決まっており、更新しないことが明らかな場合は、条件を満たさないことになる場合もあります。
また、同法第5条の2により、保育園に入れないなどの事情がある場合は、1歳6ヶ月や2歳まで延長が認められることがあります。
一方で、常用型なら、雇用が継続されていると判断されるため、取得しやすいでしょう。
また、派遣会社との間で労使協定を結んでおり、その中に「入社1年未満は除外」などの特定の条件がある場合には、取得が難しい場合もあるので、早めに会社に相談しましょう。
育児・介護休業法第6条により、労使協定で一定の労働者を適用除外とすることが認められているためです。
適用除外となるのは、例えば以下のようなケースです。
- ・継続雇用期間が1年未満の労働者
- ・申出の日から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者(1歳6ヶ月まで・2歳までの延長育休の場合は、それぞれ6ヶ月以内に雇用期間が終了することが明らかな場合)
- ・週の所定労働日数が2日以下の労働者
派遣保育士は、契約更新が前提でない登録型や、週数日のみ勤務するケースもあるため、これらの適用除外条件に当てはまる可能性があります。
自分の契約内容を確認し、必要があれば派遣会社に早めに相談しておきましょう。
育休取得の手続きをする
育休取得の条件を満たしていることがわかったら、派遣会社に「育休を取りたい」と、できるだけ早く伝えると安心です。
申請時期としては、育児・介護休業法第8条第1項により、原則として子どもの1歳の誕生日の1ヶ月前までに申し出ることが必要とされています。
また、育休を延長する場合には、育休終了予定日の2週間前までに申し出ることが原則です。
いずれの場合でも、早めに派遣会社に相談し、必要書類や手続きの流れを確認するのが重要です。
育休を無事に取得できたら、子どもを預ける保育園を探し、復帰の準備を進めるといった流れになります。
派遣保育士ならではの育休後の復帰先の決め方
育休が終わったあと、「また同じ保育園に戻れるのかな?」と心配になる方も多くいます。
正社員の場合、基本的には元の保育園に復帰することが前提です。
派遣保育士の場合は「派遣会社との契約」という形になるため、育休後にどこで働くかは、相談のうえで決まります。
たとえば、保育園側が育休を取ったスタッフの代わりに長期で働く方を雇った場合、同じ保育園に戻りにくいでしょう。
一方で、労働者派遣法第40条の2第3項により、「派遣元事業主(派遣会社)は派遣労働者が育休を取得する際に、雇用の継続を図るための措置を講じなければならない」と定められています。
この法律に基づくポイントは次の通りです。
1.派遣先に戻れない場合でも、派遣会社が新しい就業先を案内してくれる可能性がある
法律で雇用継続のための措置が義務付けられているため、育休明けに元の派遣先に戻れない場合でも、派遣会社が別の勤務先を案内してくれることがある
2. 育休を挟むと「3年ルール」がリセットされる場合がある
・育休の期間は、3年ルールの期間計算に含まれない ・育休を挟むことで、3年という期間制限がリセットされ、育休前と同じ職場で働き続けられる場合がある
ただし、これは派遣会社や派遣先の判断、契約内容によって対応が異なるため、すべての方に当てはまるわけではない点に注意が必要です。
派遣会社によっては、希望条件を丁寧にヒアリングしたうえで、これまでの勤務実績や通勤距離などを考慮して新しい園を提案してくれる場合もあります。
そのため、「戻れない=不利」ではなく、自分に合った新しい働き方を選ぶチャンスと捉えてもよいのではないでしょうか。
このように、元々の保育園に戻れない場合には、派遣会社と相談し、新しい職場で働くことになります。
育休後に派遣保育士として働くメリット
育休後に派遣保育士として働くメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- ・家庭の事情に合わせて、勤務時間の調整がしやすい
- ・さまざまな保育園で働ける
- ・ブランクがあっても働きやすい
以下から、それぞれのメリットをご紹介します。
家庭の事情に合わせて、勤務時間の調整がしやすい
派遣保育士という働き方は、ご家庭の状況に合わせて柔軟に働けるメリットがあります。
派遣会社の求人の中には「週4日勤務」「ブランクOK」など、いろいろな働き方に対応できる求人があるためです。
特に、小さい子どもがいると突然の体調不良などによって、仕事を休まなければならないときもあります。
しかし、あらかじめ勤務時間を調整しておけば、万が一の場合でも柔軟に対応できるので、復帰前の面談やヒアリングで希望条件を伝えておきましょう。
さまざまな保育園で働ける
派遣保育士として勤務する場合、さまざまな園を経験できるメリットがあります。
具体的には、「認可保育園」「企業主導型保育園」「認定こども園」などがあり、それぞれの方針や働き方で経験を積めます。
たとえば、認可保育園では保育士の人数や施設の基準が厳しく定められている一方で、企業主導型保育園は柔軟な勤務体系が導入されやすく、働き方に幅があるなど、それぞれ特徴的です。
そのため、「いろいろな保育現場を経験したい」「現在の自分に合った働き方をしたい」という方にとっておすすめの働き方です。
ブランクがあっても働きやすい
育休中はどうしても仕事から離れるため、求人はあるのかブランク期間があっても大丈夫なのか気になりますよね。
しかし、求人の中には「ブランクOK」といったものもあります。
特に保育士に特化した派遣会社の場合、保育に関係する経験やスキルを丁寧に聞き取ってくれるコーディネーターがいたり、保育園で働きやすいようなサポートが受けられたりします。
そのため、「ブランクがあるけど保育士として働きたい」という方にぴったりな働き方です。
育休後に派遣保育士として働くデメリット
育休後に派遣保育士として働くデメリットは、次の2点が挙げられます。
- ・同じ保育園で働き続けられない
- ・正社員に比べて収入は安定しない
以下から、それぞれ見ていきましょう。
同じ保育園で働き続けられない
派遣保育士として働く場合には、同じ保育園で長く働きたいと思っていても、必ずしも希望が通るわけではありません。
労働派遣法により、同一の派遣先での勤務期間は原則3年までと定められています。
ただし、派遣元での無期雇用や労使協定による延長が認められる場合もあります。
そのため、どんなに働きやすい保育園であっても、働き続けられない場合もあります。
正社員に比べて収入は安定しない
派遣保育士の場合、契約期間ごとに勤務先が変わることもあるため、次の仕事がすぐに決まらないと、空白の期間が生まれてしまいます。
派遣保育士は、時給で賃金が支払われることが多いため、空白期間や長期休暇などで出勤日数が減ると、月々の収入にも影響が出てきます。
そのため、月給制で雇用の安定している正社員に比べると、収入は安定しません。
ただし、雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金を受け取れる可能性があります。
この制度は、育児休業を取得した労働者に対し、休業開始時賃金日額の一定割合(当初6か月は67%、それ以降は50%)が支給されるもので、派遣保育士も要件を満たせば受給可能です。
一方で、「子どもが小さいうちは短い時間でいい」「体力面で休みが多いと嬉しい」といった、収入以外の面で目的がある場合には、向いている働き方になります。
育休を取った派遣保育士のリアルな体験談
実際に派遣保育士で働いていた方の育休取得のリアルな体験談をいくつかご紹介します。
登録型派遣だったので育休を取れるか不安でしたが、派遣会社に相談すると、条件を満たしているとのことで、スムーズに手続きを進められました。
育休中も電話やメールでやりとりがあり、コーディネーターさんが「復帰の時期が近づいたら条件の合う保育園を一緒に考えましょう」と言ってくれたのが心強かったです。
育休前に働いていた保育園には戻れませんでしたが、コーディネーターさんが新しい保育園を紹介してくれて、結果的には以前より条件の良い園に出会えました。
このように、同じ保育園に戻れない不安はあるものの、よりよい条件やライフステージに合った保育園で働けたケースもあるようです。
派遣保育士の育休でよくある質問
派遣保育士として働く際に、よくある質問は次の通りです。
- ・育休を延長したいけど、どうしたらいい?
- ・派遣で働くと、正社員に戻りにくい?
- ・育休と産休の取得条件や期間に差はあるの?
- ・育休中に契約が切れたらどうなる?
- ・派遣会社によって育休の対応が違うって本当?どこを選べば安心?
以下から、それぞれ見ていきましょう。
育休を延長したいけど、どうしたらいい?
育休の期間は原則として子どもが1歳になるまでです。
しかし、育児・介護休業法第5条の2により、保育園に入れないなどやむを得ない事情がある場合には、1歳6ヶ月または2歳まで延長することができます。
延長には派遣会社への再申請が必要になるため、早めの相談が安心です。
登録型派遣の場合、契約が切れてしまうと期間延長が難しいこともあるため、早めに派遣会社に相談しましょう。
派遣で働くと、正社員に戻りにくい?
派遣社員と正社員では、働き方や雇用条件が異なるため、すぐに切り替えるのは難しいこともあります。
しかし、派遣でいろいろな園を経験することで、転職活動の際に有利になることもあるので、一概に戻りにくいとはいえません。
また、「子どもが小さいうちは派遣で働きたいけど、いずれは正社員になりたい」という方もいますよね。
子どもが大きくなって、正社員に戻りたい場合には、紹介予定派遣などの直接雇用への切り替えを前提とした求人を選びましょう。
育休と産休の取得条件や期間に差はあるの?
産休と育休では、取得のタイミングや条件が異なります。
産休は出産6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産後8週間まで取得でき、雇用期間の定めのある労働者も対象。
この産前産後休業は、育児・介護休業法ではなく、労働基準法第65条に基づく制度です。
育児休業とは異なり、雇用形態にかかわらず取得できることが特徴です。
そのため、登録型派遣の保育士として働く場合、産休の方が取得しやすいといえます。
育休中に契約が切れたらどうなる?
育休中に契約期間が終了した場合、育児・介護休業法第2条に定める「育休取得の対象者=一定期間継続して雇用されている者」に該当しなくなるため、原則として育休も終了となります。
育児・介護休業法では「雇用の継続」が取得の条件とされるのです。
ただし、派遣会社が復帰後の再契約を予定している旨を明示している場合など、継続雇用の見込みが認められれば、育児・介護休業法第5条に基づいて育休継続が認められるケースもあります。
また、「育休を理由に契約終了にされた」と感じるケースでは注意が必要です。
妊娠・出産・育休を理由にする雇い止めは、男女雇用機会均等法第9条などの法律に違反する可能性があるからです。
男女雇用機会均等法第9条では、事業主が妊娠・出産・育児休業などを理由として不利益な取扱いをすることを禁じており、育休による契約打ち切りは違法と判断される可能性があります。
契約内容や終了理由が不当なものでないかを確認し、必要があれば記録を残しておくと安心でしょう。
派遣会社によって育休の対応が違うって本当?どこを選べば安心?
育休制度そのものは法律で決まっています。
しかし、実際の運用は派遣会社によって対応に差が出ます。
たとえば、育休の申請手続きについて丁寧に案内してくれる会社もあれば、曖昧な対応で積極的に対応してくれない会社もあります。
そのため、安心して育休を取りたいのなら、取得実績がある派遣会社や、担当者が親身になって相談してくれる会社を選びましょう。
派遣保育士なら育休後でも柔軟に働ける!下調べを入念にしよう
この記事では、派遣保育士でも育休を取れるのかという内容を解説しました。
わたしたち明日香では、保育士に特化した求人サービス「ずっと保育士」を運営しています。
保育士の求人に特化しているため、勤務時間・通勤距離・園の方針など、できるだけ希望条件に合った保育園を紹介します。
もし、ご興味があれば、こちらからご登録ください。
カテゴリ
保育士キャリア
ずっと保育士は、保育のお仕事を始めたい、転職・復職したい方にライフステージにあった保育のお仕事をご紹介したい。そして保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援し続けたい、という想いでサービスを運営しています。
60秒で完了!無料会員登録をする
現在、派遣保育士として働いている方や、これから派遣で働くことを考えている方にとっては、「育休は取れるの?」と不安になることもありますよね。
保育の仕事自体にやりがいを感じている一方で、子育てや体調のことを考えると、正社員としてのフルタイム勤務は不安という方も多くいます。
この記事では、派遣保育士でも育休を取れるのか、取得の流れや注意点、よくある質問とその答えについて、解説します。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
【結論】派遣保育士でも育休は取得できる
結論からいうと、いくつかの条件を満たせば、派遣保育士でも育休を取得することは可能です。
育休は「取得時の職場で継続的に雇用されていること」が前提です。
育児・介護休業法第5条において「1年以上の雇用見込みがあること」とされており、派遣でもこれを満たせば対象になります。
そのため、育休取得時に働いていた派遣会社で働き続ける予定があるかどうかが重要なポイントになります。
たとえば、これまでに契約の更新実績があったり、派遣会社側が今後も契約を更新する意向を示している場合は、「継続雇用」の条件を満たすと判断される可能性があるでしょう。
ここでいう、「育休取得時の職場」は、正社員であれば雇用先の保育園、派遣社員であれば登録している派遣会社となります。
派遣会社の対応によっては、サポート体制や取得しやすさに差が出ることもあるため、事前に対応範囲などを確認しましょう。
派遣保育士が育休を取得する流れ
派遣保育士が育休を取得する際の手続きとして、次のような流れがあります。
- ・育休取得の条件を満たしているかを確認する
- ・育休取得の手続きをする
以下から、順番に見ていきましょう。
育休取得の条件を満たしているかを確認する
派遣には仕事があるときにだけ契約を結ぶ「登録型」と、派遣会社の正社員として継続雇用を前提とした「常用型」の種類があり、育休取得時の扱いが異なります。
派遣保育士が育休を取得する際には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、育児・介護休業法)で決められた条件を満たしている必要があります。
具体的には、育児・介護休業法第5条により「子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に契約が終了しない」という条件です。
たとえば、登録型派遣では、子どもが1歳6ヶ月になる前に派遣社員としての契約の終了が決まっており、更新しないことが明らかな場合は、条件を満たさないことになる場合もあります。
また、同法第5条の2により、保育園に入れないなどの事情がある場合は、1歳6ヶ月や2歳まで延長が認められることがあります。
一方で、常用型なら、雇用が継続されていると判断されるため、取得しやすいでしょう。
また、派遣会社との間で労使協定を結んでおり、その中に「入社1年未満は除外」などの特定の条件がある場合には、取得が難しい場合もあるので、早めに会社に相談しましょう。
育児・介護休業法第6条により、労使協定で一定の労働者を適用除外とすることが認められているためです。
適用除外となるのは、例えば以下のようなケースです。
- ・継続雇用期間が1年未満の労働者
- ・申出の日から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな労働者(1歳6ヶ月まで・2歳までの延長育休の場合は、それぞれ6ヶ月以内に雇用期間が終了することが明らかな場合)
- ・週の所定労働日数が2日以下の労働者
派遣保育士は、契約更新が前提でない登録型や、週数日のみ勤務するケースもあるため、これらの適用除外条件に当てはまる可能性があります。
自分の契約内容を確認し、必要があれば派遣会社に早めに相談しておきましょう。
育休取得の手続きをする
育休取得の条件を満たしていることがわかったら、派遣会社に「育休を取りたい」と、できるだけ早く伝えると安心です。
申請時期としては、育児・介護休業法第8条第1項により、原則として子どもの1歳の誕生日の1ヶ月前までに申し出ることが必要とされています。
また、育休を延長する場合には、育休終了予定日の2週間前までに申し出ることが原則です。
いずれの場合でも、早めに派遣会社に相談し、必要書類や手続きの流れを確認するのが重要です。
育休を無事に取得できたら、子どもを預ける保育園を探し、復帰の準備を進めるといった流れになります。
派遣保育士ならではの育休後の復帰先の決め方
育休が終わったあと、「また同じ保育園に戻れるのかな?」と心配になる方も多くいます。
正社員の場合、基本的には元の保育園に復帰することが前提です。
派遣保育士の場合は「派遣会社との契約」という形になるため、育休後にどこで働くかは、相談のうえで決まります。
たとえば、保育園側が育休を取ったスタッフの代わりに長期で働く方を雇った場合、同じ保育園に戻りにくいでしょう。
一方で、労働者派遣法第40条の2第3項により、「派遣元事業主(派遣会社)は派遣労働者が育休を取得する際に、雇用の継続を図るための措置を講じなければならない」と定められています。
この法律に基づくポイントは次の通りです。
| 1.派遣先に戻れない場合でも、派遣会社が新しい就業先を案内してくれる可能性がある | 法律で雇用継続のための措置が義務付けられているため、育休明けに元の派遣先に戻れない場合でも、派遣会社が別の勤務先を案内してくれることがある |
|---|---|
| 2. 育休を挟むと「3年ルール」がリセットされる場合がある | ・育休の期間は、3年ルールの期間計算に含まれない ・育休を挟むことで、3年という期間制限がリセットされ、育休前と同じ職場で働き続けられる場合がある |
ただし、これは派遣会社や派遣先の判断、契約内容によって対応が異なるため、すべての方に当てはまるわけではない点に注意が必要です。
派遣会社によっては、希望条件を丁寧にヒアリングしたうえで、これまでの勤務実績や通勤距離などを考慮して新しい園を提案してくれる場合もあります。
そのため、「戻れない=不利」ではなく、自分に合った新しい働き方を選ぶチャンスと捉えてもよいのではないでしょうか。
このように、元々の保育園に戻れない場合には、派遣会社と相談し、新しい職場で働くことになります。
育休後に派遣保育士として働くメリット
育休後に派遣保育士として働くメリットとしては、次のような点が挙げられます。
- ・家庭の事情に合わせて、勤務時間の調整がしやすい
- ・さまざまな保育園で働ける
- ・ブランクがあっても働きやすい
以下から、それぞれのメリットをご紹介します。
家庭の事情に合わせて、勤務時間の調整がしやすい
派遣保育士という働き方は、ご家庭の状況に合わせて柔軟に働けるメリットがあります。
派遣会社の求人の中には「週4日勤務」「ブランクOK」など、いろいろな働き方に対応できる求人があるためです。
特に、小さい子どもがいると突然の体調不良などによって、仕事を休まなければならないときもあります。
しかし、あらかじめ勤務時間を調整しておけば、万が一の場合でも柔軟に対応できるので、復帰前の面談やヒアリングで希望条件を伝えておきましょう。
さまざまな保育園で働ける
派遣保育士として勤務する場合、さまざまな園を経験できるメリットがあります。
具体的には、「認可保育園」「企業主導型保育園」「認定こども園」などがあり、それぞれの方針や働き方で経験を積めます。
たとえば、認可保育園では保育士の人数や施設の基準が厳しく定められている一方で、企業主導型保育園は柔軟な勤務体系が導入されやすく、働き方に幅があるなど、それぞれ特徴的です。
そのため、「いろいろな保育現場を経験したい」「現在の自分に合った働き方をしたい」という方にとっておすすめの働き方です。
ブランクがあっても働きやすい
育休中はどうしても仕事から離れるため、求人はあるのかブランク期間があっても大丈夫なのか気になりますよね。
しかし、求人の中には「ブランクOK」といったものもあります。
特に保育士に特化した派遣会社の場合、保育に関係する経験やスキルを丁寧に聞き取ってくれるコーディネーターがいたり、保育園で働きやすいようなサポートが受けられたりします。
そのため、「ブランクがあるけど保育士として働きたい」という方にぴったりな働き方です。
育休後に派遣保育士として働くデメリット
育休後に派遣保育士として働くデメリットは、次の2点が挙げられます。
- ・同じ保育園で働き続けられない
- ・正社員に比べて収入は安定しない
以下から、それぞれ見ていきましょう。
同じ保育園で働き続けられない
派遣保育士として働く場合には、同じ保育園で長く働きたいと思っていても、必ずしも希望が通るわけではありません。
労働派遣法により、同一の派遣先での勤務期間は原則3年までと定められています。
ただし、派遣元での無期雇用や労使協定による延長が認められる場合もあります。
そのため、どんなに働きやすい保育園であっても、働き続けられない場合もあります。
正社員に比べて収入は安定しない
派遣保育士の場合、契約期間ごとに勤務先が変わることもあるため、次の仕事がすぐに決まらないと、空白の期間が生まれてしまいます。
派遣保育士は、時給で賃金が支払われることが多いため、空白期間や長期休暇などで出勤日数が減ると、月々の収入にも影響が出てきます。
そのため、月給制で雇用の安定している正社員に比べると、収入は安定しません。
ただし、雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金を受け取れる可能性があります。
この制度は、育児休業を取得した労働者に対し、休業開始時賃金日額の一定割合(当初6か月は67%、それ以降は50%)が支給されるもので、派遣保育士も要件を満たせば受給可能です。
一方で、「子どもが小さいうちは短い時間でいい」「体力面で休みが多いと嬉しい」といった、収入以外の面で目的がある場合には、向いている働き方になります。
育休を取った派遣保育士のリアルな体験談
実際に派遣保育士で働いていた方の育休取得のリアルな体験談をいくつかご紹介します。
登録型派遣だったので育休を取れるか不安でしたが、派遣会社に相談すると、条件を満たしているとのことで、スムーズに手続きを進められました。
育休中も電話やメールでやりとりがあり、コーディネーターさんが「復帰の時期が近づいたら条件の合う保育園を一緒に考えましょう」と言ってくれたのが心強かったです。
育休前に働いていた保育園には戻れませんでしたが、コーディネーターさんが新しい保育園を紹介してくれて、結果的には以前より条件の良い園に出会えました。
このように、同じ保育園に戻れない不安はあるものの、よりよい条件やライフステージに合った保育園で働けたケースもあるようです。
派遣保育士の育休でよくある質問
派遣保育士として働く際に、よくある質問は次の通りです。
- ・育休を延長したいけど、どうしたらいい?
- ・派遣で働くと、正社員に戻りにくい?
- ・育休と産休の取得条件や期間に差はあるの?
- ・育休中に契約が切れたらどうなる?
- ・派遣会社によって育休の対応が違うって本当?どこを選べば安心?
以下から、それぞれ見ていきましょう。
育休を延長したいけど、どうしたらいい?
育休の期間は原則として子どもが1歳になるまでです。
しかし、育児・介護休業法第5条の2により、保育園に入れないなどやむを得ない事情がある場合には、1歳6ヶ月または2歳まで延長することができます。
延長には派遣会社への再申請が必要になるため、早めの相談が安心です。
登録型派遣の場合、契約が切れてしまうと期間延長が難しいこともあるため、早めに派遣会社に相談しましょう。
派遣で働くと、正社員に戻りにくい?
派遣社員と正社員では、働き方や雇用条件が異なるため、すぐに切り替えるのは難しいこともあります。
しかし、派遣でいろいろな園を経験することで、転職活動の際に有利になることもあるので、一概に戻りにくいとはいえません。
また、「子どもが小さいうちは派遣で働きたいけど、いずれは正社員になりたい」という方もいますよね。
子どもが大きくなって、正社員に戻りたい場合には、紹介予定派遣などの直接雇用への切り替えを前提とした求人を選びましょう。
育休と産休の取得条件や期間に差はあるの?
産休と育休では、取得のタイミングや条件が異なります。
産休は出産6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産後8週間まで取得でき、雇用期間の定めのある労働者も対象。
この産前産後休業は、育児・介護休業法ではなく、労働基準法第65条に基づく制度です。
育児休業とは異なり、雇用形態にかかわらず取得できることが特徴です。
そのため、登録型派遣の保育士として働く場合、産休の方が取得しやすいといえます。
育休中に契約が切れたらどうなる?
育休中に契約期間が終了した場合、育児・介護休業法第2条に定める「育休取得の対象者=一定期間継続して雇用されている者」に該当しなくなるため、原則として育休も終了となります。
育児・介護休業法では「雇用の継続」が取得の条件とされるのです。
ただし、派遣会社が復帰後の再契約を予定している旨を明示している場合など、継続雇用の見込みが認められれば、育児・介護休業法第5条に基づいて育休継続が認められるケースもあります。
また、「育休を理由に契約終了にされた」と感じるケースでは注意が必要です。
妊娠・出産・育休を理由にする雇い止めは、男女雇用機会均等法第9条などの法律に違反する可能性があるからです。
男女雇用機会均等法第9条では、事業主が妊娠・出産・育児休業などを理由として不利益な取扱いをすることを禁じており、育休による契約打ち切りは違法と判断される可能性があります。
契約内容や終了理由が不当なものでないかを確認し、必要があれば記録を残しておくと安心でしょう。
派遣会社によって育休の対応が違うって本当?どこを選べば安心?
育休制度そのものは法律で決まっています。
しかし、実際の運用は派遣会社によって対応に差が出ます。
たとえば、育休の申請手続きについて丁寧に案内してくれる会社もあれば、曖昧な対応で積極的に対応してくれない会社もあります。
そのため、安心して育休を取りたいのなら、取得実績がある派遣会社や、担当者が親身になって相談してくれる会社を選びましょう。
派遣保育士なら育休後でも柔軟に働ける!下調べを入念にしよう
この記事では、派遣保育士でも育休を取れるのかという内容を解説しました。
わたしたち明日香では、保育士に特化した求人サービス「ずっと保育士」を運営しています。
保育士の求人に特化しているため、勤務時間・通勤距離・園の方針など、できるだけ希望条件に合った保育園を紹介します。
もし、ご興味があれば、こちらからご登録ください。