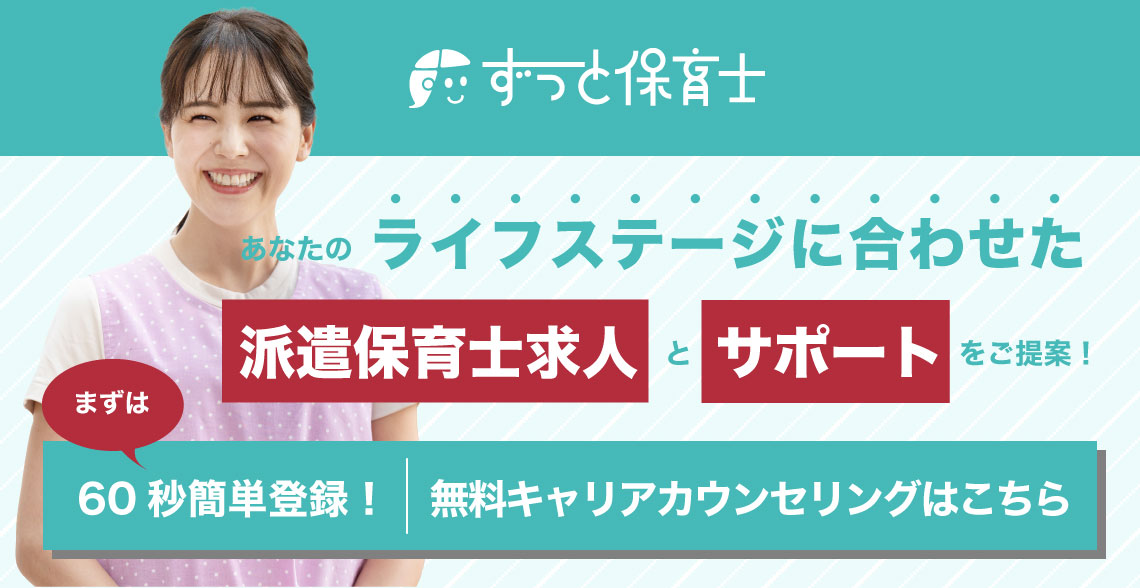派遣保育士でも有給休暇は取れる?条件・取得方法・注意点をわかりやすく解説
2025/09/11
「派遣保育士にも有給休暇ってあるの?」「あっても、実際に使えるのかな…」こうした不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
正社員と違い、派遣という立場では派遣元の企業が導入している「年次有給休暇の計画的付与制度(※労使協定に基づき、企業が有給休暇の取得日をあらかじめ定める仕組み)」などの仕組みがわかりにくく、有給の存在すら知らずに働いているケースも少なくありません。
この記事では、派遣保育士が有給休暇を取るための条件や申請方法、日数の仕組み、取りにくいときの対処法までをわかりやすく解説します。
制度を正しく理解して、無理なく自分らしく働くための一歩を踏み出しましょう。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
派遣保育士にも有給休暇はある?
派遣で働く保育士にも、有給休暇は労働基準法第39条に基づき認められています。
有給休暇は、雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば誰でも取得できる権利です。
それにもかかわらず、「派遣だから有給は使えない」と誤解している方は少なくありません。
制度を正しく知っておけば、遠慮せずに有給を活用できるとともに、安心して働き続けるための土台にもなります。
有給休暇は派遣先ではなく派遣元(派遣会社)の雇用契約が基準
派遣保育士として働く場合、有給休暇の管理は派遣先の保育園ではなく、労働者派遣法第30条の2(派遣元が労働者の労務管理を行うことが義務付けられている)などにより、雇用契約を結んでいる派遣会社が行います。
派遣先はあくまで勤務先であって、直接の雇用主ではありません。
そのため、有給休暇の申請や日程の相談も、基本的には派遣会社を通して手続きを行う仕組みになっています。
申請先を間違えてしまうとスムーズに取得できない場合もあるため、管理の主体をしっかり把握しておくことが大切です。
派遣保育士は雇用開始から6か月継続勤務すれば有給休暇がもらえる
派遣保育士が有給休暇を取得できるようになるには、雇用開始から6か月継続して勤務し、かつ全勤務日の8割以上出勤していることが条件です(労働基準法第39条より)。
たとえば、週5日勤務で6か月間に約130日出勤する予定であれば、最低でも104日以上出勤していないと条件を満たさないことになります。
6か月を約26週と仮定し、週5日勤務の場合
予定労働日数=26週×5日=約130日
出勤要件=130日×80%=104日以上
なお、実際の予定労働日数は契約内容・勤務シフト・暦によって異なります。
ご自身の雇用契約書や就業条件通知書の勤務日数をもとに、「予定労働日数 × 0.8(80%)」で出勤要件を計算してください。
これは労働基準法で定められた共通のルールであり、正社員やパートだけでなく、派遣保育士にも適用されます。
6か月に満たない場合は原則として有給は付与されないため、まずはこの基準を満たすことがスタートラインとなります。
派遣保育士の有給休暇の取得方法は派遣会社に申請するだけ
有給休暇を取りたいときは、勤務先の保育園ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社に申請します。
有給の管理は労働基準法第39条に基づき派遣会社が行う義務となっており、取得希望の連絡も基本的に派遣会社を通じて行います。
労働契約が派遣会社と結ばれているため、派遣先には休暇の管理義務がないためです。
申請方法は会社ごとに異なりますが、口頭や書面などの指定に従えば問題ありません。
まずは、自分の派遣会社でどのような手続きが必要かを確認しておきましょう。
派遣保育士の有給休暇に関する注意点
ここでは、有給休暇を実際に取るうえで気をつけたいポイントを整理して紹介します。
- 有給休暇はできるだけ早めに申請する
- 拒否されたり取りづらいと感じたら派遣会社に対応してもらう
- 派遣会社によって保育士の有給の取りやすさは違う
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
取得したいときはできるだけ早めに申請する
有給休暇を取得したい場合は、できるだけ早めに派遣会社へ申請しましょう。
特に保育現場は人員調整が重要なため、事前に日程を伝えることでスムーズに取得しやすくなります。
有給休暇の取得は労働者の「時季指定権」として認められているため、原則として直前の申請であっても法的には問題ありません。
ただし、派遣先や派遣元の業務運営に著しい支障が生じると判断されれば、企業側の「時季変更権」により取得日を変更される可能性があります。
そのため、直前の申請であっても法的には問題ありませんが、繁忙期や急な欠勤が重なる時期などは、周囲への配慮を意識した対応も必要です。
申請時には理由を伝える義務はない
有給休暇の申請にあたって、理由を伝える義務はありません。
労働基準法では、取得にあたって具体的な理由を申告する必要はないとされています。
しかし会社によっては確認のために任意で理由を聞かれることもあります。
ただし、たとえば病欠や家庭の事情などでの取得の場合、職場の理解を得やすくするためにあえて伝えるケースもあります。
また、トラブルを避けるために簡単に事情を説明する方もいるものの、あくまで強制ではないことを覚えておきましょう。
拒否されたり取りづらいと感じたら派遣会社に対応してもらう
有給休暇は労働者の正当な権利であり、理由なく取得を拒否されることは法律に反します。
企業側には「時季変更権」と呼ばれる制度がありますが、これはあくまで業務に著しい支障が出る場合に限り、取得時期を変更できるものです。
たとえば、インフルエンザの集団感染で複数人が欠勤している場合や、年度末の保護者対応などで極端に業務が集中している場合などが、時季変更権の対象になる可能性があります。
単に繁忙期だから、人手が足りないからといった理由では認められません。
それでも取得が難しいと感じた場合は、派遣会社の相談窓口や、必要に応じて労働基準監督署(最寄りの労働局)に相談しましょう。
さらに深刻なケースでは、弁護士など専門家に相談することも検討できます。
その際には、勤務日数や有給申請の履歴、担当者とのやり取り内容などをメモしておくとスムーズです。
派遣会社によって保育士の有給の取りやすさは違う
派遣保育士にとって、有給休暇が「取得しやすいかどうか」は派遣会社によって差があります。
法律上のルールは同じでも、以下のように実際の運用方法やサポート体制の違いによって、働きやすさに大きく影響することがあります。
派遣会社によって制度運用やサポート体制が異なる
有給休暇の申請がしやすいかどうかは、派遣会社の制度運用やサポート体制に大きく左右されます。
たとえば、申請フローが簡単で説明が丁寧な会社や、相談窓口が設けられている会社では取得へのハードルが下がります。
また、派遣先との調整をスムーズに進めてくれるかどうかも重要なポイントです。
派遣会社を選ぶ際は有給制度の対応も確認する
長く働くことを考えるなら、有給休暇の取りやすさも派遣会社選びの判断材料に加えましょう。
たとえば、「有給取得の実績があるか」「制度説明が丁寧か」「相談窓口の有無」など、事前に確認できる項目は意外と多くあります。
制度そのものがあるだけでなく、実際に「使いやすいかどうか」を見極めることが大切です。
派遣保育士の有給休暇付与日数
ここでは、派遣保育士に与えられる有給休暇の日数について、勤務日数や勤続年数ごとの違いをわかりやすく紹介します。
- 付与日数は週の所定労働日数に応じて決まる
- 勤続年数に応じて付与日数が増えていく
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
付与日数は週の所定労働日数に応じて決まる
有給休暇の日数は、週に働く日数によって異なります(厚生労働省資料より)。
たとえば、週5日勤務の場合は初年度に10日付与されるのが基本です。
一方で、週3~4日勤務などの短時間労働者は「比例付与」という仕組みにより、勤務日数に応じた日数が与えられます。
派遣保育士は、曜日によって勤務日が異なるシフト制で働くケースや、週2~4日のみ勤務する短時間契約なども多いため、週の労働日数をしっかり確認しておくことが大切です。
付与日数は勤続年数に応じて増えていく
有給休暇は、6か月の勤務で最初に付与されたあと、勤続年数が1年ごとに増えるたびに付与日数も増えていきます。
たとえば、週5日勤務のケースでは、最初の6か月後に10日、その後1年ごとに11日、12日…と増えていき、6年6か月以上勤務すると年20日付与されるようになります(労働基準法第39条より)。
派遣であっても、同じ派遣会社と継続的に雇用関係が続いていれば、正社員と同じように付与日数が増えていく仕組みです。
派遣保育士の有給休暇についてよくある質問
ここでは、派遣保育士として働くなかでよく寄せられる有給休暇に関する疑問について、ひとつずつわかりやすく解説します。
- 有給休暇を取ると給料は減るの?
- 有給休暇の繰越や時効ってあるの?
- 契約期間の途中で辞めたら有給休暇はどうなる?
実際に有給休暇を取得する際の、参考にしてください。
有給休暇を取ると給料は減るの?
有給休暇を取得しても、その分の給与は減りません。
これは、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第39条により、「所定労働日に年次有給休暇を取得した場合は、通常の賃金を支払うこと」と定められているからです。
欠勤扱いになることはなく、給与明細には「有給休暇」や「年休」などの項目で記載されることが一般的です。
「特別休暇」は会社ごとに定められる別制度であるため、通常は区別して記載されます。
出勤した日と同様に、1日分の賃金がきちんと支払われますので、安心して取得しましょう。
有給休暇の繰越や時効ってあるの?
有給休暇には付与日から2年間の有効期限があり、取得しないまま期限を過ぎると自動的に消滅してしまいます。
たとえば、2025年4月に付与された有給は、原則として2027年3月までが使用期限となります。
1年間で使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2年目以降は消えるため注意が必要です。
契約期間の途中で辞めたら有給休暇はどうなる?
契約の途中で退職する場合でも、残っている有給休暇は原則として取得できます。
退職日までに使い切れるよう、あらかじめ計画的に申請しておくことが大切です。
派遣会社によっては、事前に申請すれば退職前にまとめて有給を取得できるよう配慮してくれることもあります。
なお、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合、派遣会社によっては買い取りに応じることもあります。
ただし、労働基準法では、在職中に有給休暇を買い取ることは原則として禁止されています(労働基準法第39条の趣旨による)。
一方、退職により消化できなかった有給休暇については、労働者の権利が失われる前提であるため、買い取りが認められるケースもあります。
同時に、買い取りは会社にとって法律上の義務ではありません。
まずは事前に派遣会社へ確認しておくことをおすすめします。
派遣保育士でも有給休暇は取れる!正しく理解して活用しよう
ここまで、派遣保育士の有給休暇について詳しく見てきました。
派遣保育士であっても、有給休暇はしっかりと法律で認められた権利です。
6か月以上働き、出勤率が8割を超えれば取得できる仕組みになっており、日数は勤務日数や勤続年数によって増えていきます。
申請は派遣会社に行い、早めに相談しておくのがスムーズに取るコツです。
万が一、取りづらさを感じた場合でも、拒否は原則できないことを知っておきましょう。
有給を安心して使えるかどうかは、派遣会社のサポート体制にも関係しますが、制度を正しく理解して、無理のない働き方を選ぶことが大切です。
「ずっと保育士」では、派遣保育士の方が有給休暇をきちんと取得できるよう、制度の説明や申請時のサポートにも丁寧に対応しています。
勤務日数や契約状況に合わせた個別のご相談にも対応していますので、不安な点があればいつでもお問い合わせください。
安心して長く働けるよう、一人ひとりに合った働き方を一緒に考えていきます。
カテゴリ
保育士キャリア
ずっと保育士は、保育のお仕事を始めたい、転職・復職したい方にライフステージにあった保育のお仕事をご紹介したい。そして保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援し続けたい、という想いでサービスを運営しています。
60秒で完了!無料会員登録をする
「派遣保育士にも有給休暇ってあるの?」「あっても、実際に使えるのかな…」こうした不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
正社員と違い、派遣という立場では派遣元の企業が導入している「年次有給休暇の計画的付与制度(※労使協定に基づき、企業が有給休暇の取得日をあらかじめ定める仕組み)」などの仕組みがわかりにくく、有給の存在すら知らずに働いているケースも少なくありません。
この記事では、派遣保育士が有給休暇を取るための条件や申請方法、日数の仕組み、取りにくいときの対処法までをわかりやすく解説します。
制度を正しく理解して、無理なく自分らしく働くための一歩を踏み出しましょう。

【記事監修】ずっと保育士編集部
「ずっと保育士」は、保育ひとすじ28年の株式会社明日香が運営する保育専門のキャリアサポートサービスです。結婚や出産、育児など、目まぐるしく変わるライフステージの中で、その時その時にぴったり合うお仕事を紹介したい。そして、保育の仕事でずっと輝き続けるあなたを応援したい、という想いで保育士の就職、転職、復職などのキャリア支援を行っています。また、「ずっと保育士」では保育士さんの疑問や悩みなどを少しでも解決すべくコラムを通した情報発信も積極的に行っています。
派遣保育士にも有給休暇はある?
派遣で働く保育士にも、有給休暇は労働基準法第39条に基づき認められています。
有給休暇は、雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせば誰でも取得できる権利です。
それにもかかわらず、「派遣だから有給は使えない」と誤解している方は少なくありません。
制度を正しく知っておけば、遠慮せずに有給を活用できるとともに、安心して働き続けるための土台にもなります。
有給休暇は派遣先ではなく派遣元(派遣会社)の雇用契約が基準
派遣保育士として働く場合、有給休暇の管理は派遣先の保育園ではなく、労働者派遣法第30条の2(派遣元が労働者の労務管理を行うことが義務付けられている)などにより、雇用契約を結んでいる派遣会社が行います。
派遣先はあくまで勤務先であって、直接の雇用主ではありません。
そのため、有給休暇の申請や日程の相談も、基本的には派遣会社を通して手続きを行う仕組みになっています。
申請先を間違えてしまうとスムーズに取得できない場合もあるため、管理の主体をしっかり把握しておくことが大切です。
派遣保育士は雇用開始から6か月継続勤務すれば有給休暇がもらえる
派遣保育士が有給休暇を取得できるようになるには、雇用開始から6か月継続して勤務し、かつ全勤務日の8割以上出勤していることが条件です(労働基準法第39条より)。
たとえば、週5日勤務で6か月間に約130日出勤する予定であれば、最低でも104日以上出勤していないと条件を満たさないことになります。
6か月を約26週と仮定し、週5日勤務の場合
予定労働日数=26週×5日=約130日
出勤要件=130日×80%=104日以上
なお、実際の予定労働日数は契約内容・勤務シフト・暦によって異なります。
ご自身の雇用契約書や就業条件通知書の勤務日数をもとに、「予定労働日数 × 0.8(80%)」で出勤要件を計算してください。
これは労働基準法で定められた共通のルールであり、正社員やパートだけでなく、派遣保育士にも適用されます。
6か月に満たない場合は原則として有給は付与されないため、まずはこの基準を満たすことがスタートラインとなります。
派遣保育士の有給休暇の取得方法は派遣会社に申請するだけ
有給休暇を取りたいときは、勤務先の保育園ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社に申請します。
有給の管理は労働基準法第39条に基づき派遣会社が行う義務となっており、取得希望の連絡も基本的に派遣会社を通じて行います。
労働契約が派遣会社と結ばれているため、派遣先には休暇の管理義務がないためです。
申請方法は会社ごとに異なりますが、口頭や書面などの指定に従えば問題ありません。
まずは、自分の派遣会社でどのような手続きが必要かを確認しておきましょう。
派遣保育士の有給休暇に関する注意点
ここでは、有給休暇を実際に取るうえで気をつけたいポイントを整理して紹介します。
- 有給休暇はできるだけ早めに申請する
- 拒否されたり取りづらいと感じたら派遣会社に対応してもらう
- 派遣会社によって保育士の有給の取りやすさは違う
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
取得したいときはできるだけ早めに申請する
有給休暇を取得したい場合は、できるだけ早めに派遣会社へ申請しましょう。
特に保育現場は人員調整が重要なため、事前に日程を伝えることでスムーズに取得しやすくなります。
有給休暇の取得は労働者の「時季指定権」として認められているため、原則として直前の申請であっても法的には問題ありません。
ただし、派遣先や派遣元の業務運営に著しい支障が生じると判断されれば、企業側の「時季変更権」により取得日を変更される可能性があります。
そのため、直前の申請であっても法的には問題ありませんが、繁忙期や急な欠勤が重なる時期などは、周囲への配慮を意識した対応も必要です。
申請時には理由を伝える義務はない
有給休暇の申請にあたって、理由を伝える義務はありません。
労働基準法では、取得にあたって具体的な理由を申告する必要はないとされています。
しかし会社によっては確認のために任意で理由を聞かれることもあります。
ただし、たとえば病欠や家庭の事情などでの取得の場合、職場の理解を得やすくするためにあえて伝えるケースもあります。
また、トラブルを避けるために簡単に事情を説明する方もいるものの、あくまで強制ではないことを覚えておきましょう。
拒否されたり取りづらいと感じたら派遣会社に対応してもらう
有給休暇は労働者の正当な権利であり、理由なく取得を拒否されることは法律に反します。
企業側には「時季変更権」と呼ばれる制度がありますが、これはあくまで業務に著しい支障が出る場合に限り、取得時期を変更できるものです。
たとえば、インフルエンザの集団感染で複数人が欠勤している場合や、年度末の保護者対応などで極端に業務が集中している場合などが、時季変更権の対象になる可能性があります。
単に繁忙期だから、人手が足りないからといった理由では認められません。
それでも取得が難しいと感じた場合は、派遣会社の相談窓口や、必要に応じて労働基準監督署(最寄りの労働局)に相談しましょう。
さらに深刻なケースでは、弁護士など専門家に相談することも検討できます。
その際には、勤務日数や有給申請の履歴、担当者とのやり取り内容などをメモしておくとスムーズです。
派遣会社によって保育士の有給の取りやすさは違う
派遣保育士にとって、有給休暇が「取得しやすいかどうか」は派遣会社によって差があります。
法律上のルールは同じでも、以下のように実際の運用方法やサポート体制の違いによって、働きやすさに大きく影響することがあります。
派遣会社によって制度運用やサポート体制が異なる
有給休暇の申請がしやすいかどうかは、派遣会社の制度運用やサポート体制に大きく左右されます。
たとえば、申請フローが簡単で説明が丁寧な会社や、相談窓口が設けられている会社では取得へのハードルが下がります。
また、派遣先との調整をスムーズに進めてくれるかどうかも重要なポイントです。
派遣会社を選ぶ際は有給制度の対応も確認する
長く働くことを考えるなら、有給休暇の取りやすさも派遣会社選びの判断材料に加えましょう。
たとえば、「有給取得の実績があるか」「制度説明が丁寧か」「相談窓口の有無」など、事前に確認できる項目は意外と多くあります。
制度そのものがあるだけでなく、実際に「使いやすいかどうか」を見極めることが大切です。
派遣保育士の有給休暇付与日数
ここでは、派遣保育士に与えられる有給休暇の日数について、勤務日数や勤続年数ごとの違いをわかりやすく紹介します。
- 付与日数は週の所定労働日数に応じて決まる
- 勤続年数に応じて付与日数が増えていく
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
付与日数は週の所定労働日数に応じて決まる
有給休暇の日数は、週に働く日数によって異なります(厚生労働省資料より)。
たとえば、週5日勤務の場合は初年度に10日付与されるのが基本です。
一方で、週3~4日勤務などの短時間労働者は「比例付与」という仕組みにより、勤務日数に応じた日数が与えられます。
派遣保育士は、曜日によって勤務日が異なるシフト制で働くケースや、週2~4日のみ勤務する短時間契約なども多いため、週の労働日数をしっかり確認しておくことが大切です。
付与日数は勤続年数に応じて増えていく
有給休暇は、6か月の勤務で最初に付与されたあと、勤続年数が1年ごとに増えるたびに付与日数も増えていきます。
たとえば、週5日勤務のケースでは、最初の6か月後に10日、その後1年ごとに11日、12日…と増えていき、6年6か月以上勤務すると年20日付与されるようになります(労働基準法第39条より)。
派遣であっても、同じ派遣会社と継続的に雇用関係が続いていれば、正社員と同じように付与日数が増えていく仕組みです。
派遣保育士の有給休暇についてよくある質問
ここでは、派遣保育士として働くなかでよく寄せられる有給休暇に関する疑問について、ひとつずつわかりやすく解説します。
- 有給休暇を取ると給料は減るの?
- 有給休暇の繰越や時効ってあるの?
- 契約期間の途中で辞めたら有給休暇はどうなる?
実際に有給休暇を取得する際の、参考にしてください。
有給休暇を取ると給料は減るの?
有給休暇を取得しても、その分の給与は減りません。
これは、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第39条により、「所定労働日に年次有給休暇を取得した場合は、通常の賃金を支払うこと」と定められているからです。
欠勤扱いになることはなく、給与明細には「有給休暇」や「年休」などの項目で記載されることが一般的です。
「特別休暇」は会社ごとに定められる別制度であるため、通常は区別して記載されます。
出勤した日と同様に、1日分の賃金がきちんと支払われますので、安心して取得しましょう。
有給休暇の繰越や時効ってあるの?
有給休暇には付与日から2年間の有効期限があり、取得しないまま期限を過ぎると自動的に消滅してしまいます。
たとえば、2025年4月に付与された有給は、原則として2027年3月までが使用期限となります。
1年間で使い切れなかった分は翌年に繰り越せますが、2年目以降は消えるため注意が必要です。
契約期間の途中で辞めたら有給休暇はどうなる?
契約の途中で退職する場合でも、残っている有給休暇は原則として取得できます。
退職日までに使い切れるよう、あらかじめ計画的に申請しておくことが大切です。
派遣会社によっては、事前に申請すれば退職前にまとめて有給を取得できるよう配慮してくれることもあります。
なお、退職時に未消化の有給休暇が残っている場合、派遣会社によっては買い取りに応じることもあります。
ただし、労働基準法では、在職中に有給休暇を買い取ることは原則として禁止されています(労働基準法第39条の趣旨による)。
一方、退職により消化できなかった有給休暇については、労働者の権利が失われる前提であるため、買い取りが認められるケースもあります。
同時に、買い取りは会社にとって法律上の義務ではありません。
まずは事前に派遣会社へ確認しておくことをおすすめします。
派遣保育士でも有給休暇は取れる!正しく理解して活用しよう
ここまで、派遣保育士の有給休暇について詳しく見てきました。
派遣保育士であっても、有給休暇はしっかりと法律で認められた権利です。
6か月以上働き、出勤率が8割を超えれば取得できる仕組みになっており、日数は勤務日数や勤続年数によって増えていきます。
申請は派遣会社に行い、早めに相談しておくのがスムーズに取るコツです。
万が一、取りづらさを感じた場合でも、拒否は原則できないことを知っておきましょう。
有給を安心して使えるかどうかは、派遣会社のサポート体制にも関係しますが、制度を正しく理解して、無理のない働き方を選ぶことが大切です。
「ずっと保育士」では、派遣保育士の方が有給休暇をきちんと取得できるよう、制度の説明や申請時のサポートにも丁寧に対応しています。
勤務日数や契約状況に合わせた個別のご相談にも対応していますので、不安な点があればいつでもお問い合わせください。
安心して長く働けるよう、一人ひとりに合った働き方を一緒に考えていきます。